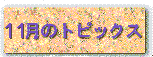
�@�܂��i�w����������5�����̗A����n���́A�����Ӗ�����̂�
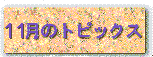 |
�R�X����o�̒�~���\�ɑ����A�i�w�������̒�~�\ �@�܂��i�w����������5�����̗A����n���́A�����Ӗ�����̂� |
 ���{�̐������̔z�u�Ɓ@���̔\��
���{�̐������̔z�u�Ɓ@���̔\���܂��́A�Ζ��A�����\��2012�N8�������݂̑S���e�n�̐������̕��z�Ɛ����\�͂ł��B
�S���e�n�ɕ��U���Ă���Ƃ������́A�֓��Ɗ��ɕ݂��Ă���ƌ�����ł��傤�B
�����n�̋߂��ɂ���ƌ�������܂łł����A�����͗���ƌ����Ă���A��s����
���C�A����C�A��C�n�k���l����ƁA���Ȃ�S�z�Ȕz�u�ł��邱�Ƃ��킩��܂�
 ���{�̐������̐����\�͂̐��ڂƉғ���
���{�̐������̐����\�͂̐��ڂƉғ������́A�����\�͂Ƃ��̉ғ����̐��ڕ\�ł��B12�N���̒����P�ʂŌ���ƁA���v���Ƃ�������
���v���k�Ƃ����[���ȃ��x���ł��B�����\�͂́A2000�N����2011�N��12�N�ԂŁA��16.4�����팸
���܂������A����ł��A2005�N�x��87���Ƃ��������ғ������ێ��ł����A���̌�6�N�ԂŐ��Y�ʂ�
17���������B�ғ�����74���ɒቺ���A�Œ��̑��u�Y�ƂƂ��ẮA���ɐ[���Ȓ�ғ����ł��B
�N�@�x�@�� 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 �����\�͐�a�c 5,355 5,274 4,967 4,835 4,965 4,770 4,830 4,895 4,834 4,793 4,616 4,479 �N�x���ωғ����� 79.1 81.0 81.4 83.0 84.4 87.2 82.9 82.7 78.9 74.5 77.8 74.2 �Ζ����i���Y���j�k 22,183 2,1651 21,892 22,115 21,745 22,397 21,432 21,771 20,880 19,638 19,497 18,544
 ���낵���Â����{�̐�����
���낵���Â����{�̐��������L�\�́A���{�̊e�������̏v�H�N�ł��B�ŏ��̏v�H�N�ɑS�\�͂�����������ł͂Ȃ�
���̌�A�g�b�p�[���lj���������Ă���̂ŁA�����܂Ŗڈ��Ƃ��Č��Ē��������̂ł����A
����ɂ��Ă����ɌÂ����Ƃ��������蒸����Ǝv���܂��B
 �؍��̐������̔z�u�Ƃ��̔\��
�؍��̐������̔z�u�Ƃ��̔\�����Ɋ؍��̐������̔\�ׂ͂Ă݂܂����B�܂������̂͂��̋K�͂œ��{�̐��{�ł��B
���̔\�͍������邾���ł��A���̌�����R�X�g�����͂ɁA�����̈Ⴂ�����肻���ł��B
�܂����L�̓��{�n�}����́A�����m������^���J�[�œ��{�C���ɂ����ė�����A
�؍�������{�C���o�Ē��ڂ����ė��������y���ɋ߂��A�D�^�����������Ƃ��z���o���܂��B
�@�@�������̃^���N�e�ʁ@�y�с@�^���N��́@���А���
�Ж��i�O���[�v�j �������� �v�H�N �\�͂a�c �ԍ� �i�w�������� �^���N�e�� � �ԍ� �r�j�@�G�i�W�[ �U�R�E���T�� 1962�N 840 �@ ���@�G 46,230�j�k -- �J �m��C���`���� 1969�N 275 �A �V�X 68,126�j�k 19 �K �f�r�J���e�b�N�X �퐅�@���X 1967�N 680 �B ���V�� 120,530KL 21 �L �r-�I�C�� ���R�I���T�� 1976�N 575 �C �x�@�R 699,898KL -- �M ����I�C���o���N ��R�@�e�T�� 1964�N 395 �D ���@�� 106,219KL 27 �N
���Ȃ݂Ɋ؍��̐������̏v�H�N�ׂĂ݂܂������A�؍������������Â����Ƃ�������܂�����
���L�̃A�W�A�����̐������\�͐��ڕ\�������������B���{��1980�N����т��Č����ł���
�؍���1995�N����2005�N�ɑ啝�������Ă��܂��B�v����ɐV�����ݔ��Ȃ̂ł��B���̕\�����
�؍��Ƃ̌�������R�X�g�����ɂ����āA���{�̗͖Ƃ�Ȃ��ł��낤�Ǝv���܂��B
 �i�w�G�l���M�[���@���{�C���̖�������5������A����n��
�i�w�G�l���M�[���@���{�C���̖�������5������A����n��10��30���̔R�������V���̋L���ɂ��A�i�w�͓��{�C���y�ѓ��{�C����A�N�Z�X���e�Ղ�
�V�X���܂߂āA5�̖������ɕېŃ^���N��u���A�A����n���������̕�����܂����B
�i�w�̂g�o�ł͔��\����Ă��Ȃ������̂ŁA�����̓Ǝ���ނ̂悤�ł����A��ώQ�l�ɂȂ�܂��B
������11�����A�؍������瓔�����̐��i�A�����J�n����Ƃ̓��e���L�ڂ���Ă��܂����B
���͂��̖������̗A����n���́A��ΎO�����炢�̂��炵�����f�Ǝ��s���Ǝv���܂��B
�@�@�k�Б�B�`���ł��\���グ���ʂ�A��s�����A���C�A����C�A��C�n�k���l����A
�@�@�������̑S�Ă������m���Ȃ̂ł��B��������{�C�ɐ��������ڂ����Ƃ͏o���܂��A
�@�@�������̔\�͂����A���i���~������A������x�J�o�[���A�k�Б�ɂ��Ȃ�܂��B
�A�@���{�C���̐��i�A����n�Ƃ����؍�����߂����n�������������Ẵ��[�R�X�g��
�@�@���ݓ��{�C���ɂ͑傫�Ȑ������͂���܂���B�]���ċ��l����Ő��Y�����Ζ����i��
�@�@���{�{�y�����āA���{�C�ɗA�����Ă��܂��B���������̒n�}�����Ă��A�؍�����A��
�@�@��������A�������߂��A�y���Ƀ��[�R�X�g�ŋ����ł��邱�Ƃ��z���ł��܂��B
�B�@����n������`���A�ɂ₩�Ɍ�������Ă������낤���Ƃւ̑����Ή�
�@�@�i�w��11��2���ɂȂ��Ĕ��\���܂������A�����������̕��Ƃ�͂薧�ڂɊW���Ă��܂��B
 ���o�V����m�g�j�����A�i�w�G�l���M�[������������~�@�i�w��11/2�ɔ��\
���o�V����m�g�j�����A�i�w�G�l���M�[������������~�@�i�w��11/2�ɔ��\10��28���̓��j�̓��o����1�ʂɁu�i�w�G�l������������~14�N�t�@�����\��13���팸�v��
��X�I�Ɍf�ڂ���܂����B�m�g�j��1�����߂��̎��Ԃ����������l�̓��e��������Ă��܂����B
����ɑ��i�w�́A11��2���ɁA�قڕ̒ʂ�̓��e�����\���܂����B�v���
�@1�@�Q�O�P�S�N�R�����@����������~�i�툳�������u�̔p�~�j����B
�@2�@�V���ɐݔ����������{���A���u�����p���Ζ����w���i�̐������_�Ƃ���B
�@3�@�Ή��H�ꉻ��́A�r�j�O���[�v�ƍ��قŊ؍��ɐV�݂���p���L�V���������ݔ��p��
�@�@�@�����ƂȂ�A���}��ޓ��̐����E�A�o���s���B
�@4�@ �Ζ����i�̕������_�Ƃ��Ă̖������@�\�͑�������B
����̔��\�ł͐G����Ă��܂��A����̔p�~�́A��͂�o���̓��R�����\���_��
�قڌ��肵�Ă��Ǝv���܂��B���\�̃^�C�~���O�́A�r�j�ƌ_���n����ł��傤�B
���́A�i�w�Əo���̊W�́A���ԂŌ����Ă�����A�[���A�����Đe�����Ǝv���܂��B
��r����̂��悢���͕ʂƂ��āA���Ȃ��Ƃ��i�w�ƃR�X���̊W�悢�ł��傤�B���������I��
�����̂́A�o�����ɐ������̕��̎����Ǝv���܂��B���Ђg�o�@2003�N1�����Q���B
�o�����ɂ̕��ɂ��s�����镪���A�����̐V���̐����ň�����ɓ������āA
���ɐ������̓P�ޔ�p�̈ꕔ��V�������T����ɕ��S�����H�Ƃ����b������ʂł��B
���l�ɁA��N�̏o���̓��R�������̕����i�w�̖����z�ł̃o�[�^�[���������܂̂ŁA
���̑��ŁA�k�C���ł͏o���̓Ϗ��q���c���A�i�w�̎������~����̂́A��ʓI�ɂ�
���R���Ɓu�Z�b�g�v�ƍl�����Ă���̂ŁA�ƊE�l�Ȃ玞�Ԃ̖��Ǝv���Ă������Ƃł��傤�B
�������A�}�X�R�~�͔��\������I��肩������܂��A�i�w�͂��ꂩ�炪��ς��Ǝv���܂��B
�Ή��H��Ƃ��Ă͎c��̂ŁA�n�������̂ւ́̕A�����͐������₷���Ǝv���܂���
����ł��Ј��̓]�₲�Ƒ��A���ɂ��q�l�������ʂ��w�Z�܂ł��l����Ƒ�ς��Ǝv���܂��B
 ���x���@�́u�d�������u�ݔ�����v�̒B�����\�͍팸�̒�`�H�@2013/2/15�NjL
���x���@�́u�d�������u�ݔ�����v�̒B�����\�͍팸�̒�`�H�@2013/2/15�NjL�ł͊e�Ђ̔\�͍팸���\�ŁA���x���@�̏d�������u�̑������̊�͒B������̂��B
���́A�e�Ђ̂g�o���ׂĂ��A����ݔ��\�͂̐��m�Ȑ����͌f�ڂ���Ă��܂���ł����B
�]���ďڍׂȋL���������ƕ]���̍����u�T���_�C�������h2010�N6��22�������v�����ɁA����ȍ~
���u�̑��݂́A���Ă̓��R���̉��ǁi+3��j�݂̂Ƃ��팸���\��̔\�͂ōČv�Z���܂����B
���_�́A�i�w�A�o���A���a�V�F���͒B���A�R�X���͂��Ɩ�50���B�V���R�͂���153���ł�����
2013/2/14�ɐ��-68��A�a�̎R-38��ƕ���+3.45��i�eBD�j�\���ăN�����[�ł��B
�d�������u�̑����� �������̉��P�� ���x���@�v�Z��@�Ⴆ��2010�N���_��
�\�͂�51���a�c�A���u��5���a�c�Ȃ�
������10��������9.8���Ȃ̂ŁA���̊�Ƃ�
9.8���w1.45��14.2���܂ʼn��P�̕K�v������B
���ꂪ���L�\�̖ڕW�������ƂȂ��Ă��܂��B10%�����̊�� 45%�ȏ� 10%�ȏ�13%�����̊�� 30%�ȏ� 13%�ȏ�̊�� 15%�ȏ� ���č���̌��ň�����^��Ɏv�������Ƃ�����܂����B����́A�\�͍팸�̒�`�ł��B
�O���[�v��
�P�ʐ�a�c2008�N
���\��
��N���u
�����\����N��
�������ڕW
�������ڕW
�\��14�N3��
�팸��
�\�͗\��14�N3��
���u
�������B���@���B���̔���
���B�̏ꍇ�̕s�����i�w�G�l���M�[ 1792 206 11.5% 15.0% 1373 1212 17.0% ������~�ŒB������ �o�@�� 640 83 13.0% 14.9% 557 520 16.0% ���R�팸�ŒB������ ���a�V�F�� 515 88 17.1% 19.7% 447 395 20.8% �120�p�~�ŒB���� ���R�[�l���� 661 28+3��31 4.236% 6.14% 505 556 6.20% ����+3.45���-67�a�̎R-38 �R�@�X�@�� 635 25 3.94% 5.71% 438 495 5.05% ��o���\���57�s��
�^��̂��������́A2011�N3��15���B�R�X���Ζ����A�l���s��50000�a�c�A��o��30000�a�c�B
�܂��i�w�������`�a�ō��킹��19800�a�c�̔\�͑����̓͏o�����A�������Y�ɓ����Ă���̂ł��B
�k�Ђ���͂�4���ԂŁA�ݔ��\�͂̑����H���ȂǏo�����͂Ȃ��̂ŁA�v����ɂ���ȑO��
�\�͍팸���ɁA���ۂɐݔ��p���������̂ł͂Ȃ��������A�ݔ��l�`�w�܂ŗ]�T������A�k�Ќ�
���ޏ�̔\�͂�ݔ��\�͈�t�ɏグ�Đ\�������̂��Ǝv���܂��B����A�䓖�ǂɎf���A
�ݔ��p�����A��v������p�̕K�v������B�����Ȃ�ƍ���X���c�����Ă���@2008�N�̊�N
�̔\�͂��{���ɐݔ��l�`�w�\�͂Ȃ̂��Ƃ����^����N���Ă��܂��B����������ĕ��܂��B