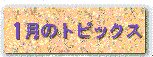
弊社所長会のディスカッション内容の紹介も含め考えてみました
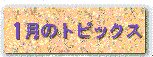 |
2009年 世界&日本経済、石油SS業界はどうなるのか 弊社所長会のディスカッション内容の紹介も含め考えてみました |
 ビッグ3はもつのか。その再生方法はあるのか
ビッグ3はもつのか。その再生方法はあるのか米国を代表する自動車産業のビッグ3は、経営危機に瀕しています。再生法は、議会で
討議されていたもののぎりぎりで否決。しかしそれでも「大きすぎてつぶせない」のか
ブッシュ大統領は、金融安定化法で場つなぎをしました。しかしこれは、人間の病気なら
下血を止めないまま、輸血をしているようなもので根本的な解決ではありません。
これが銀行や保険業なら、負の遺産を血を出して切り捨てれば、会社は存続出来ると
思いますが、もの作りであるメーカーは、燃費が良く、環境にもやさしく日本車と対等に
競える魅力ある自動車が、1-2年で出来るとは思えませんので本当に深刻な状態です。
更に色々な意味で非常に強い力をもつと言われている全米自動車労組。その複雑な
関係は良く分かりませんが、本気で再生をするならば、国家管理のもとチャプター11に
より一度破産させてから出直すしか、再生の方法はないでしょう。
 米自動車産業有識者よりコメントを頂きましたので 追加掲載します 1/7追加
米自動車産業有識者よりコメントを頂きましたので 追加掲載します 1/7追加米国で一台あたりの車の生産コストを考える時、過去の退職者ので含めた労働者の
年金等の社会保険等のコストは、何と日本の10倍だそうです。では労組が悪いので
しょうか。実は、そうとも言えません。それは日本と国の社会システムが違うからだ
そうです。例えば米国の医療費は高額で有名ですが、健康保険も入れない階層が
全国民の約二割もいるそうです。一方日本では、健康保険に入れない子供等がニュ
ースになる程なのでごく少数でしょう。要する日本では年金や社会保険や福祉に至る
まで国が中心となってやってはおりますが、米国ではこれを企業というか業界がやる
とかなり昔に決めたそうです。よって日本の年金制度等が財政上極めて厳しい状態に
ありますが、同様なことが全米の自動車労組にも重く圧し掛かっているのだそうです。
またその方曰く、アメリカは、ごく少数の都市部以外、車しか移動の手段がないので
今でも車を買いたい人は、一杯いるそうです。しかし自動車クレジット会社に現在お金
がないので、信用の高い普通の人に対してもローンが組めない状態となっている。
従って、金融安定化法で、自動車会社そのものではなく、自動車金融会社に資金を
投入するには、それなりの意味があるそうです。最後に驚いたのは、米国の国民性
をよく知るその方は、意外に回復は早い(本年中)のではないかとのことことでした。
 アメリカ経済の基幹製造産業に何がのこっているのか
アメリカ経済の基幹製造産業に何がのこっているのか「ビッグ3以外に米国の有名企業は、どんな名前が思い浮かぶか」と所長会で聞いて
みました。すぐ出てきたのは、マイクロソフト、インテル、グーグル、コカコーラ、GE。
では、純粋なメーカーに絞って考え直してみてと問い直すと、ボーイング社。あとは、
なかなか思い浮かばないので、世界の大企業ランキングをネットで検索してみました。
売上高で第一位が小売業のウォールマートで、あとは石油のメジャーや金融や保険、
通信です。メーカーらしき業種は、ヒューレットパッカード(HP)やIBMが41位と42位。
デルが102位ですが、パソコンはメーカーというよりは、システム設計や開発が命で、
単に組み立てているだけという人もいるので、純粋なメーカーとは少し違うのかもしれ
ません。化粧品や医療のジョンソン&ジョンソンは、112位。ファイザーは115位。マイクロ
ソフトやインテルは、139位と183位。あとは、ペプシコーラコカコーラ、マクドナルドです
から、メーカーとしては程遠い状況です。(フォーチュン2007 統計資料のメモルビアより)
もしかしたら米国の物づくりは、兵器産業か宇宙産業、あるいはボーイングやダグ
ラスのような航空機産業しか残っていないのではないかと心配になるほどです。
将来ある若い人が、理工化系の大学を出ても、銀行やヘッジファンドに就職し、
その数学的知識を駆使して、良く分からない金融商品を作る。あるいは絶対負け
ない運用ディーラーシステムを作って、自らディーラーとなり年収数億円を稼ぐ。
要するにいつしか地道な物作りが軽んじられ、労せずして稼ぐことがアメリカン
ドリームの象徴になってしまったのではないでしょうか。
私の友人で、経済学者かつ作家の浜田和幸氏は、「アメリカのみならず、ドルが崩壊し
世界の基軸通貨でなくなるかもしれない」と警告しています。もしアメリカが開き直れば、
日本や中国や世界がもっている米国債は紙くずです。その開き直った時の最後の
アメリカの底力は何でしょうか。まずは世界一の軍事力。結果として過去の大不況は、
戦争で乗り切ったと言われています。そして今、決してアメリカが起した訳ではありま
せんが、年末のイスラエルによるのガザ地区の空爆は非常に心配です。二つ目は、
農業。食料自給率100%と言った方がいいかもしれません。そして最後は、エネルギー
自給率です。アラスカ等の石油埋蔵量を考えれば、エネルギー自給率もほぼ100%です。
 当社HPでも紹介した あの「ドバイ」もついにバブル崩壊か
当社HPでも紹介した あの「ドバイ」もついにバブル崩壊か秋頃以降、多くの友人から「ドバイもバブル崩壊というニュース見ました。垣見さんの
言うとおりになりましたね」というメールを頂きました。その一つが、12月 5日(金) 11時
10分に配信されたのダイヤモンドオンラインの「砂上の楼閣」だった ドバイ不動産開発
バブルの崩壊です。そして決定的なのが12月17日、テレビ朝日午後10時放送の
ニュースステーションでの約20分にも渡るドバイのバブル崩壊を伝える特集でした。
実は、本HP3月企画の「アブダビ国営石油訪問記&ドバイ経済の繁栄は本物か」は
業界外の方からも大人気でした。Yahoo検索で「ドバイ訪問」では何と第一位でヒット
します。更に「ドバイの繁栄」でも第二位と三位にヒットします。また株式新聞にも
原油の話としてですが2008年4月14日と16日の二回に亘って紹介されました。
そしてテレビ朝日のニュースステーション以降、再びアクセスが急増しているのです。
ちなみに5月18日に放送されたNHKの「沸騰都市」も第1回はドバイで、私はビデオに
とってしっかり見ました。そして今もう一度見ても、この繁栄はバブルではないかと
危険視する内容はほとんどなく、むしろサブプライムローン問題で欧米の証券市場の
株価が下落する中、行き場を失った資金は、ドバイ証券市場に入り、1日で10%も
上がったという内容で始まっています。
しかしこのバブル崩壊。HPでも紹介した通り、ドバイ原油は、もう8万BDしか産出して
いませんので問題は深刻です。それにここ数年の好景気で作ったものは、世界一の
搭ブルジュ・ドバイや、パームジュメイラ、ザワールド、更にユニバース等の海上の
人口島のリゾートや超豪華なホテル等で、不況時に役に立つものはありません。
同じ投資をするにしても、太陽光発電とか潮流発電とか、その後の経済回復の為
の、例えば工場の誘致をローコストで出来るような実体経済の役に立つものは、
ほとんどないに等しいでしょう。金融、観光、物流拠点が経済の三本柱ですが、
唯一の実業である物流拠点だけでも、中継基地としての繁栄を期待しています。
 そもそも何が悪かったのか。その答えは「お金=通貨とは何か」を考えると分かる
そもそも何が悪かったのか。その答えは「お金=通貨とは何か」を考えると分かるこの話題も12月の所長会で討議して、皆目から鱗状態だったのでご紹介します。
大昔の人類は、食料等必要な物を「物々交換」で得ていたと考えられます。例えば、
海辺の漁民は、魚や貝を採り、農耕民族は穀物を作り、狩猟民族は動物を採ります。
しかし魚や肉は、干したり燻製にしたりしても保存には限界があります。従って余った
物を物々交換により、自分たちにはない必要な物を得ようとしたのではないでしょうか。
しかし猪一頭は、魚何匹に相当するのか。お米だったらどの量に相当するのか。
またその交換レートも、豊作か飢饉か等の自然状況により大きく変化したでしょう。
そうなると物々交換では、限界があります。そこで人類は、その取引を円滑にするため
お金=通貨というシステムを考えたのではないかと思います。従ってお金の役割は、
「物の価値の基準や尺度」、「物(価値)の交換(の円滑化)」、そして「価値の保存」
ではないかと思います。そしてそのシステムは「信用」によって維持されるのです。
やがて農耕が農業となり、中世には工業も起こりました。正にもの作りです。同時に
商業や物流も含めたサービス業的なものを発展して来たでしょう。ここまではすべて
「実業」です。その意味では、お金は、産業なり経済なりの各取引を円滑にするため
の道具に過ぎず、お金は、「主」ではなく本来「従」の存在であるべきなのです。
こう考えるとイスラム教では、お金がお金を生む「金利」を禁止しているそうですが、
その意図している意味が良く分かります。
しかし近代は、金利はまだいいとしても、金融派生商品やそれを何倍にも拡大する
バレッジで、もうマネーゲームすなわちギャンブルです。それでも株のように全体の
市場が、大きくなるのあれば、全員が儲けることも出来るのかもしれませんが、各国
通貨の変動を商品としたFX取引などは、完全にギャンブルで、勝者の影に必ず敗者
がいます。秩序ある日本は、ギャンブルは原則禁止で、競馬も競輪も競艇も限られた
ところしか出来ないのに、金融市場のギャンブルは、野放しにしてよいのでしょうか。
特にアメリカの金融市場は、自由とは名ばかりで、何でもありの完全な無責任市場
となってしまいました。その意味で米国は、当局もそしてウォール街でギャンブルに
興じていた全ての人が、多いに反省し、悔い改める必要があると思います。 その
反省なくして金融経済の再生もまたないでしょう。
 日本の実態経済の大底はいつか。その時の日経平均は、回復はいつか
日本の実態経済の大底はいつか。その時の日経平均は、回復はいつか私は当初、日本の実態経済をここまで悪化するとは予想していませんでした。
すなわち日本の金融機関はサブプライムローンの不良債権を余りもっていなかった。
仮に保有していたとしてもその金融機関や投資家が、その保有分の損を出せば済む。
それこそ、トヨタが不良債権をもっている訳ではないからです。従って株価は売られ
過ぎのはずでした。しかし今から思えば、トヨタ等日本企業は輸出に依存していた
為に、世界経済の影響をまともに受けることとなりました。更に円高です。その結果
売られ過ぎと思っていた株価が正しかったのかもしれません。
しかしトヨタ等の自動車会社より、先に表面化したのは、マンション等ディベロッパー
です。その後、自動車とか家電とかの派遣切りが発表され、そちらに目が行きがち
ですが、マンションが悪いなら次はゼネコンが心配です。12月は何とか乗り切った
ようですが、その筋の情報によれば、「007と中小ゼネコンは二度死ぬ」との笑えない
ジョークを聞きました。建設業界は、下請けから孫受けまで裾野が広いので心配です。
具体的には、最悪期は、3月から7月上旬にかけて、東証の日経平均でボトム7000円
割れで止まれば、よし。しかし最悪は5000円割れもありうると覚悟しています。
そして気になる日本の実態経済の回復時期ですが、早い人は今年の秋以降回復
と見ている人もいますが、私は遅い方の2-3年以上かかると覚悟しています。
 原油価格はどこまで下がるか 今は「リバウンド」で下がりすぎ
原油価格はどこまで下がるか 今は「リバウンド」で下がりすぎ では話を原油と石油に戻しましょう。NYのWTI原油価格は、7月11日歴史的な147ドルを
記録した以降、暴落状態も歴史的でした。今までの日足ではとても画面で表現出来ない
ので、「週足」でに変更して初めて分かるのですが、現在の30ドル台の水準は、四年前の
レベルです。正に4年かけて上昇した分をたったの5ヶ月で下落してしまいました。
高騰時は6月企画 歴史的転換点を迎えた原油価格 で またNY WTI 相場が「ギャン
ブル場」と化していたという怒りは、10月企画をご覧下さい。
しかしそのギャンブルは今でも続いているのでしょうか。12/19の終値 33.89ドル/Bに対し
12/21の始値が42.79ドル/Bと、26%も上昇。この時点ではまで、イスラエルとパレスチナの
紛争は全く発生していないのにこの乱高下です。もはやNY のNTMEXは正常な原油価格
指標として、相応しくないのではないかと心配しています。
では、ドバイやオマーンの中東原油価格は正常なのでしょうか。実はこの答えもNOです。
3月企画でご紹介したとおり、現物と信じていた中東原油でさえ、プラッツ社の提供する
電子市場でやりとりされ、現物の引き取り義務はありません。従って先物でないだけで、
やはりギャンブルになる可能性は未だに否定出来ません。
さて改めて原油価格のあるべき姿を考えて見ます。オイルサンド等の代替燃料コストから
逆算すれば50ドル/B。開発者の利益を含め上限70ドルが適正だと本HPでも紹介しました。
今もそのレベルで良いと私は思っています。99.7%を輸入する日本にとって、安ければ安い
程良さそうですが、安い=新規の原油開発は進みませんから、安い=近い将来の暴騰要因
となります。また 30ドル以下では、一見安定しているように見えるサウジ等も国内問題が
一気に噴出し、政情不安になるのではなかいと心配しています。あくまで私見ですが、
50ドル/B程度が望ましいと思います。
 国内ガソリン市況は
国内ガソリン市況は下記の表は石油情報センターが毎週調査し、発表している国内ガソリン市況です。
しかし実態が更に安いのは、読者の皆様もご存知の通りです。東京と言う高コスト地区の
ガソリン 8/4 8/11 8/18 8/25 9/1 9/8 9/16 9/22 9/29 10/6 10/13 10/20 10/27 価 格 185.1 184.4 183.2 181.7 176.2 174.5 173.0 171.5 170.2 164.7 161.6 157.4 151.3 下げ幅 ピーク -0.7 -1.9 -3.4 -8.9 -10.6 -12.1 -13.6 -14.9 -20.4 -23.5 -27.7 -33.8 ガソリン 11/3 11/10 11/17 11/25 12/8 12/15 12/22 1/5 1/12 1/19 1/26 2/2 2/9 価 格 141.0 136.6 132.0 127.9 119.1 114.7 110.6 106.8 下げ幅 -44.1 -48.5 -53.1 -57.2 -66.0 -70.4 -74.5 -78.3 -. -. -. .
弊社直営でさえ、12月29日現在の販売価格は、最高値でも105円、最安値は100円です。
いつもなら、「上げる時は早いのに、下げる時はゆっくりなのはおかしい」とお叱りを頂く
一般消費者からのメール 今回ばかりは、むしろご心配頂いているようです。
しかし原油価格は 12/19の33ドルがどう見ても当面の底値です。1/6現在、50ドルへ約1.5倍
も急上昇しました。そしてイスラエルとパレスチナの戦争が中長期化すれば更に高騰するで
しょう。そうなれば、元売も本気で生産調整し、需要に見合う生産となれば、まずTOCOMが
上がり、そして海RIM価格は適正水準に戻るでしょう。その時は、最大 10 円あった仕切差は
5円以下まで縮小され、市況正常化の最後のきっかけとなるのではないとか思っています。
事実、1/7頃から若干値上げするSSも見られてきました。
 元売再編は加速せざるを得ない
元売再編は加速せざるを得ない現在の石油&SS業界の収益状態は、ガソリン価格のページで分析している通り、誰も
儲からず、誰もやって行けないレベルです。業界NO1の新日石と言えども、本年3月期の
決算は、最低でも3500億円の赤字と聞いています。これでは、他の元売が本当にもつのか
心配です。このようなHPを運営しておりますと、色々な方が、様々な情報を教えてくれます。
新たなる再編の可能性についても同様ですが、とてもHPで公開出来るような内容ではない
ので、皆様のご推測にお任せします。一つだけ言えることは、何が起こってもおかしくない
と言うことです。新日石と新日鉱の経営統合に関するコメントは、昨年12月企画の通り。
 2009年3月末 SS数はどこまで減るか
2009年3月末 SS数はどこまで減るか今回の原油暴落に始まり、新仕切り体系の週決め効果。需要収縮による需給緩和。
そして過当競争の結果SS業者は、大変疲弊しています。このまま行けば、本年3月末の
全国のSS数は前年の44000より大幅に減って、限りなく4万SSに近づくでしょう。そして
心配されるのは、SS過疎問題です。過疎問題は本HPでも、いつか取り上げてみます。
 我々SSは、どうすれば良いのか
我々SSは、どうすれば良いのかではSS業界に未来はないのでしょうか。勝ち残るSSが2万あるとすれば、そのコンセプト
も2万通りあるでしょう。その根底に共通するのは、「真の顧客満足サービスの徹底」だと
思います。その実現は、スパルタでやらせるのではなく、やりたくなる仕組みを作り、それが
従業員にとっても自己の向上に繋がるよう会社も配慮し、会社と従業員の目的や利害の
べクトルを合わせればよいのです。
その具体的な方法は、高圧的な教育ではなく、自ら気付いてもらうコーチングでしょう。
明日から売上が上がるキャンペーン等とは違い、一見遠回りのようですが、最もまともな
近道だと思います。この結論は実は昨年と同様ですが、弊社はその基本理念を信じて、
今年も1年頑張りたいと思います。本年もどうぞよろしくお願いします。
ご意見ご要望ご感想はこちらから 垣見 裕司 2009年1月7日 再更新 Ver3