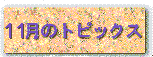
発表までの裏話、見直される軽油とディーゼルハイブリッドへの期待
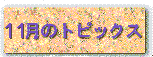 |
石油業界の快挙!、サルファーフリー燃料供給開始へ 発表までの裏話、見直される軽油とディーゼルハイブリッドへの期待 |
 サルファーフリーとは何か
サルファーフリーとは何かサルファとは、ずはり硫黄(S)のことです。燃料等に硫黄が多く混入されていると、排ガスの中に
硫黄酸化物(SOx)が排出されたり、窒素酸化物(NOx)が増加したり、不完全燃焼等で燃え残った
「すす」等が、粒子状物質(SPM)となったりして、人体や環境に影響を及ぼす諸悪の根源とされて
来ました。この硫黄分を減らすのが「低硫黄化」、更に10PPM (PPMは百万分の1)のまで低減
する事を、事実上すべて取り除いたの同等の効果と言う意味で「サルファーフリー」と言います。
東京都の規制で装着が義務付けられるようになったDPF(ディーゼルパティキュレートフィルター)も
性能を発揮し、東京都の空気汚染は大幅に改善していますが、軽油のサルファーフリーにより
DPFの耐久性が大幅に向上するだけでなく、より一層排出ガスを綺麗にしてくれる、とのことです。
 今まではどのくらいの硫黄が含まれていたのか
今まではどのくらいの硫黄が含まれていたのかでは、過去からの涙ぐましい、硫黄分の削減の歴史をご紹介しましょう。
第一段階 ディーゼル車から排出されるNOx排出量を減らす為に必要なEGR装置(排ガス再循環)
への対応の為、1992年10月から、5,000ppm以下から2,000ppm以下まで低減しました。
第二段階 PMの排出量を減らす為の排ガス後処理装置(酸化触媒やトラップオキシダイザー)
への対応の為、1997年7月から、500ppm以下まで低減しました。
第三段階 2005年の新長期規制に向けたディーゼル車の排ガス対策として、 DPF(前述)等の
後処理装置の導入が必要とされ、 ガソリン同様に2004年末までに硫黄分を500ppm以下から
50ppm以下とする規制を決定。 こうした中石油業界は、大気環境対策を先進的に進めている
東京都などからの強い要請に対し、 自主的な取り組みとして、2003年4月、規制時期より1年
9ヶ月前倒して、50ppm軽油の全国販売を開始しました。
過去からの硫黄削減の経緯を表にまとめてみましたのでご覧下さい。
単位PPM 1976年以前 1976-1992 1992-1997 1997-2003/4 2003/4-2004/12 2005/1以降 硫黄含有量 12,000以下 5,000以下 2,000以下 500以下 50以下 10以下
30年前の公害時代まで遡らなくても、ついこの前のバブル期でさえ、5000PPMもあったかと思うと
一市民としては、ぞっとします。それでは、国の法律等の規制値は、どうなっていたのでしょうか。
2004年末までは500PPM、2006年末までが50PPM、そして2007年以降が10PPMですから、2年も
前倒ししての実施は、正に快挙と言えるでしょう。東京都もそのHPで高く評価しています。
 サルファーフリーガソリン&軽油は、とのくらい環境に良いのか
サルファーフリーガソリン&軽油は、とのくらい環境に良いのかでは、サルファーフリー燃料によって、環境汚染等はどのくらい改善されるのでしょうか。
石原都知事が、ビンに黒い「スス」を入れて振っていたので印象的な粒子状物質(PM、SPM)が
何と99%、窒素酸化物(NOx)が55%以上、削減されると言われています。これらは、DPF、特に
連続再生型の実質能力の向上、耐久性の向上、NOx吸蔵還元型触媒、更には、NOx PM同時
低減型触媒の普及との相乗効果ですが、誠に嬉しくなる数字です。
またエンジンの燃費もよくなのとのことなので、軽油ディーゼルエンジンに限っても2010年時点
で年間70万tも削減されるとのことです。
こんな難しい話を持ち出すまでもなく、最近街中で荷物を積載したトラックが加速している時も
いわゆる「黒煙」はほとんど見なくなりました。環状8号線から西に100mのところに住んでいる私
としては、子供達の事を考えると誠に嬉しい限りです。ちなみに、下図は、東京都のHPに掲載
されていた、10/29 11時現在のリアルタイムでの SPM の 東京都内分布図です。
さして風の強い日ではないので、奥多摩地方と都心の値が大して変わらないことは、この
硫黄分削減をはじめ、DPF等を装着したトラック業界やご当局のご指導の賜物でしょう。
 海外の規制を調べてみると
海外の規制を調べてみると過去の例から言えば、米カリフォルニア州の排ガス規制ではありませんが、日本が一番
遅れているようなイメージを持ってしまいますが、現実はどうなのでしょうか。
現実を調べて見ると、実はアメリカが一番甘く、現時点は、ガソリン300PPM、軽油で500PPM
将来も、ガソリンが2006年から60PPM、軽油が2010年から15PPMです。
また欧州の方は、現時点が、ガソリン150PPM、軽油350PPM、2005年から、ガソリン50PPM
2008年から10PPM、軽油は2005年から50PPM、2009年から10PPMと日本に続くレベルなので
日本の石油業界は、日本の国に対しても国民に対しても、多いにアピール出来るレベルでは
ないでしょうか。石油連盟の方で、資料を出していたので、図を引用させて頂きました。
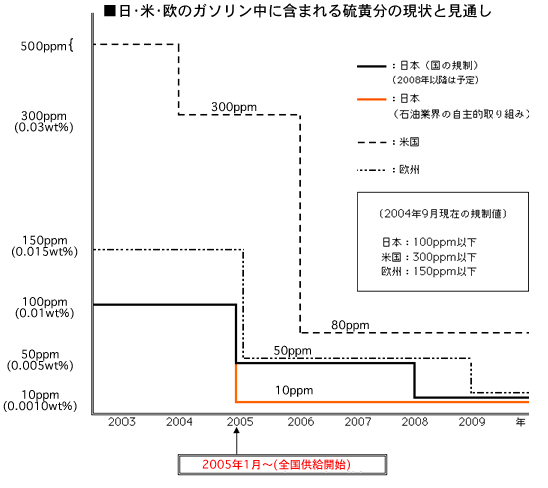 _
_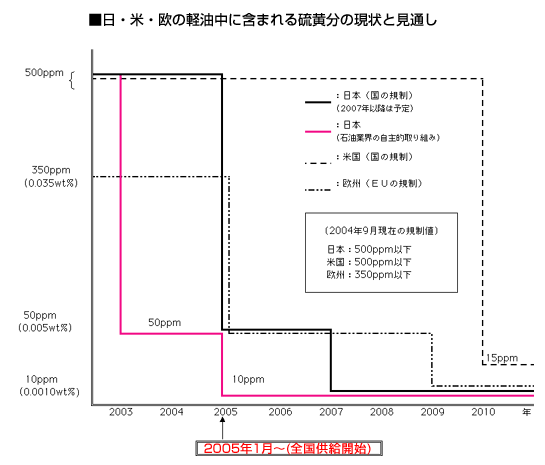
 気になる対応費用は?、製品価格は上がるのか
気になる対応費用は?、製品価格は上がるのかでは石油業界としてこのサルファーフリーの実現のために、どのくらいの対策費用が必要だった
のでしょうか。石油連盟では研究開発費から設備投資まで「2500億円」を投じたと報じています。
ちなみに2003年度の総消費量は8月企画でご報告の通り、ガソリン6200万KL、軽油3873万KL
ですから、合計約1億KLです。2500億円を1億KLで割ると、2.5円/Lとなります。
三年償却ならこの1/3の0.8円/L、5年償却なら 0.5円/L。当初は、業界で負担しきれないので、
消費者の皆様にも是非ご負担をお願いしたいと言っていた元売各社でしたが、その後の原油の
大幅値上げという荒波の中に没した感じがあり、今現在、特約店に対し、サルファーフリー化に
伴う値上げの話はまだ来ていないのが実情です。
余談ですが、元売各社の2004年12月末期や2005年3月末期の決算は、前年比も大幅改善が
見込まれていますし、国も多少の補助金を出したそうなので、元売の社会的使命として、価格
には、既に織り込まれているもの、と信じております。
 石油連盟、統一見解までの裏話
石油連盟、統一見解までの裏話ところでその2500億円の投資の裏には、元売各社固有の事情があったようです。
比較的最初から投資に積極的だった民族系と、慎重というか「欧米の規制値から見ても日本は
充分先行しているのだから、法規制を満たせば良いではないか」という消極的な外資系との
間には、問題に対するスタンスやその意欲に、かなりの違いがあったのではないかと思います。
その実施が各社の個別対応となるか、或いは石油連盟元売全社が一斉スタートとなるのか
微妙だった時期もあったようですが、ご当局の「トップランナー方式で行こう」というご指導と
石油連盟トップのリーダーシップによって、一斉スタートが実現されたのではないかと、業界人
として、そして一国民として今回の石油連盟の決定を高く評価している次第です。
しかし昨今の外資の経営判断スタンスは、ある意味では極めて一致しています。これはあくまで
個人的な感想ですが、当時の日本石油に興亜石油の持ち株を売ったカルテックス。BPの小売業
からの撤退。エクソンとモービルの合併とその後の日本での対応。ロイヤルダッチシェルの昭和
シェル株のサウジアラムコへの一部売却。これの事実は、「世界第3位の消費国である日本の
マーケットの重要性は変わらない」といくら声高に叫んでも、少なくとも過去からの相対論では、
明らかにそれが減っていることを表していると思います。
 設備投資をしなかった元売の精製能力は落ちるのか
設備投資をしなかった元売の精製能力は落ちるのかでは積極的に投資をしなかった一部の外資系は、どうやってサルファーフリーに対応するので
しょうか。ネット等で教えて戴いた話しなので、なんとも言えませんが、「処理速度を落として
脱硫のレベルを上げている」と聞いています。正しいかは分りませんが、能力の同じフィルターが
あるとして、そこをゆっくり通せば不純物はより多く取り除ける、という理解で良いのかと思います。
では、投資をしなかった一部の外資系のガソリンと軽油の生産能力が落ちて、ガソリンの業転
相場が益々上がるのか、と心配しましたが、更にマニヤックな方の話としては、「軽油をより脱硫
する為に処理速度を落すと、その軽油の一部がガソリンにまで分解されてしまう。昨今の灯油と
軽油の業転が高いのは、その為だ」と言う人もあり、「秋にガソリン業転が弱含んだのは、10PPM
に対応しないガソリンの在庫を放出した一次的要素だ」と教えてくれる人もあり、「単に灯油の
在庫を貯めるたに灯油に合わせた原油処理をしているだけで、サルファーフリー問題とは
関係ない」という人もあり、私も、どの見方が正しいのか分りません。
少なくとも 各製油所や精製設備、更には脱硫方法やその設備によって違うでしょうし、私は
精製設備の専門家ではないので、後は読者の皆様にご判断戴けば幸いです。
 今度は自動車業界の番 期待されるリーンバーン、直噴、そしてディーゼルエンジン
今度は自動車業界の番 期待されるリーンバーン、直噴、そしてディーゼルエンジン今まで排気ガス問題となると、自動車業界と石油業界は、対立とは言わないまでも、良い協調参考資料 「 【日本よ】石原慎太郎 国政の怠慢」 10/4(月) 産経新聞
関係をとっているとは、言えませんでした。例えば、前回の東京都の例を見ても、サルファー
フリー等燃料品質の改善が先で、そうでないと、DPFは触媒の性能や耐久性に問題が出る
等のコメント等があったかと思います。石油業界はじっとこらえて、いよいよサルファーフリーを
実現しました。今度は、自動車業界の出番でしょう。
例えば、2010年の燃費基準の達成の為には、リーンバーン(希薄燃料燃焼)エンジンや、
シリンダーに直接ガソリンを噴射する直噴エンジンが有効とされて来ましたが、既存エンジンに
比べ、Noxの発生量が多くなるのが難点で、NOx吸蔵還元触媒の装着が不可欠でした。
しかし、今までは、この触媒が硫黄によって被毒が発生し、この再生には、燃料を使った
再加熱が必要でした。よってガソリンのサルファーフリーは、触媒の性能や耐久性が大幅に
向上するだけでなく再加熱に使っていた燃料の分も燃費の向上に繋がるので、正に1石3鳥です。
またディーゼルエンジンの燃費やパワーは以前から知られていましたが、何故か日本では
あまり高い評価を受けていませんでした。それはやはり、トラックの排ガスやあの「すす」から
来るイメージが多少なりとも影響していたでしょう。
しかし、あのトヨタに言わせれば、水素の燃料電池車が一般普及するまでは、軽油のディーゼル
エンジンによるハイブリッド車がもっとも有効であると言っています。
ディーゼルエンジンのもう一つの難点は、振動と音ですが、深夜の住宅地の車庫入れ等で、
気を使った経験のある人も、ハイブリット車なら当社企画でもご報告の通り、微速ではエンジン
オフのバッテリー走行ですから、この振動と音から実質的に開放される日も近いでしょう。
自動車からの排ガスを低減するためには、自動車技術と燃料品質の両面からその対策を
進めて行くことが極めて重要でしょう。1997年から、財団法人石油産業活性化センターと、
財団法人、日本自動車研究所が、実施している Japan Clean Air Program(JCPN)を国の
補助で立ち上げていますが、両業界が、日本のそして世界の環境の為、一致協力して
問題解決にあたって戴けることを切に希望します。