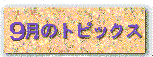
今年だけで3度目の大幅値上げとなる末端市況を考える
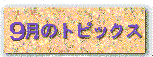 |
史上初 WTI $50/B突破寸前(その後下落)の原油市況と 今年だけで3度目の大幅値上げとなる末端市況を考える |
 イラク戦争終結?にも関わらず、何故原油価格は高騰を続けるのか。
イラク戦争終結?にも関わらず、何故原油価格は高騰を続けるのか。産油国別原油価格ぺージ や財務省発表の原油 通関統計ページ でもご紹介している通り
現在の原油価格は、昨年2月のイラク開戦時の水準を突破し、90年の湾岸戦争を上回りました。
6月こそ一段落し「いよいよ反落時期か」との販売業者の期待に反して、7月から再び1本調子で
上昇を続け、8月に入ってからは、「史上最高値更新」が連日のように聞かれるようになりました。
ニューヨークの先物市場の「WTI原油」も1983年の取引開始以来の最高値を更新し、8/19の
終値で$48.7/B、翌8/20の午前中には$49.4/Bという$50/Bの大台直前まで高騰しました。
前回企画で何度も申し上げているようにイラクでの大規模な戦闘は既に終結しているにも
関わらず、何故ここまで原油価格が高騰し、その高値を維持し続けているのでしょうか。
原油価格の高騰原因として一般的に言われているのは、中国と米国の旺盛な需要と米国の
低在庫、そして戦争終結後も思うように生産を回復出来ないイラクの要因でしょう。
前回企画以後発生した新たな高値要因としては、ロシアの大手石油会社ユコスの経営危機や
ベネズエラの政治不安等がありますが、やはり高値の主犯は、中東全体の緊張状態を過度に
煽っている「投機筋」の動きであることは4月企画でも申し上げたとおりです。
WTIが最高値を付けた直後から5$近く下落し、8/30には$42.3/Bまで下落するなど荒っぽい動き
を見せていることが、その証拠のような気がします。
しかし投機筋の影響を受けやすいWTIのみならず、実需を反映し、OPECが指標にしている原油
7種類のバスケット価格も 1980年11月以来、実に23年9ヶ月ぶりに$40を突破したことは、我々
実業を営む者にとって極めて深刻な状況だと思います。
ある程度の高値を容認してきたOPECも流石に高すぎると判断したのか、7月と8月の2度に亘る
計250万BDの増産の発表も、実際のところはヤミ増産の追認に過ぎず、一時的な反落はする
ものの、プライスバンドの上限でる$28という本来の価格には遠く及ばない動きとなっており、
その意味ではWTIの8月最終週の下落傾向が本物かどうか今後注視していきたいと思います。
では究極の高値要因は何でしょうか。前回同様全くの私見ですが、現実には3000万BDを超えて
いると言われている実際の生産量を冷静に考えると、仮にOPECが、9月に再度150BDの増産を
発表したとしても、それも現状追認であり、実質的な増産余力は、サウジしかないこと。
そして実は「そのサウジでさえも本当の生産余力がどのくらいあるのか未知数である」と市場が
判断しているのではないかと思います。これを書いている8/31は、WTIで$43/Bと、多少一服した
感はありますが、相変わらず超高値での、もみ合いが続いていることは確かです。
 元売各社の長年の設備廃棄が功を奏し、高騰を続ける業転市況
元売各社の長年の設備廃棄が功を奏し、高騰を続ける業転市況次に元売と商社や大手特約店間の取引指標として重要な業転市況について考えてみます。
下記表の通りガソリン業転市況は、昨年12月の80.6円/Lの水準から上昇を始めました。
6月の97.9円までほぼ1本調子で値上がりを続け、ボトム比なんと17.3円/Lも上昇しました。
原油CIFが昨年10月の19.57円から6月の25.90円まで6.3円しか上昇していないので、一見すると
便乗値上げのようですが、精製設備の地道な廃棄という努力を続けて来た結果、その
「需給バランスを反映している価格」なら、それはやむを得ないでしょう。
そして海外の原油市況がやや緩んだ6月(下記表は日本到着CIF価格なので約1ヶ月遅れ)
を反映した7月に、それと連動するかの様に(但し精製設備の定期修理明け等の要因もあるが)
業転価格が若干緩みましたが、8月には再び98円近くまで上昇し、我々販売業者の期待は、
原油価格同様に裏切られることとなりました。
この業転市場の追い風を受けた石油元売各社は、4月に3円、6月4円、そしてこの9月にも4円
と合計10円近いの値上げを発表しました。しかしこれは建値ベースの話で、これに業転価格
連動方式の値上げ分が加算されたり、激戦市況での「特価」が廃止されたりして、場所によっては
15円以上も近く仕切UPとなったSSもあることでしょう。
そして今回の値上げで業界では「系列回帰」という言葉が「流行語」となりました。系列高の
業転(ノンブランド)安という長年の環境のもとで、今まで系列元売の「サインポールを返せ」という
逆鱗に触れない程度で、安い業転を買って命を繋いで来たSSが、下記表の業転高騰の通り
「 系列安 < 業転高 」となったために、系列から引取るようになったことを表す言葉です。
よってこの系列回帰をしたSSにとっての実質的な仕入価格コストUPは、今まで系列より業転が
安かった価格幅の例えば4円に今回の元売建値値上げが加わることになり、大幅となりました。
同様に業転を買わないまでも、業転価格を反映するような価格決定方式を採用していた商社や
大手特約店にとっても、実質値上げは、15円近くになのかもしれません。
 それを裏付ける、エネ庁発表の系列卸価格
それを裏付ける、エネ庁発表の系列卸価格
上記表の8月9月は、当社の推定です。
さてエネ庁が石油情報センター経由でSSから毎月収集する卸価格は非常に参考になります。
例えば、1月のボトム価格の88.9円が、3月までに1.1円是正され90円となり、4月の系列元売の
3円値上げで4月に+1.9円 、5月に更に+1円で、計92.9円と元売方針の通り値上げが浸透した
ことが分ります。6月の元売 3円値上げも、6月7月の2ヶ月間の出来上がりで97円となっており
我々買手側としては、見事に取り切られた事を如実に示しております。
これを元に 8月と9月を推定してみると、業転の再高値を反映して、8月もじりじり上がり、9月の
4円という大幅値上げも、「原油の歴史的な高騰」という紛れもない事実とともに、受け入れて
いかなければならないと思っております。
 原油値上げと元売仕切値上げを徐々に反映していく末端市場
原油値上げと元売仕切値上げを徐々に反映していく末端市場それでは、肝心の末端市況は、どうなっているのでしょうか。
まずは、A列の石油情報センター発表の全国市況を見てみましょう。
原油価格や業転価格がほぼ底であった年末の末端価格は、税抜きで100円/L。それが3月まで
続き消費税の総額表示と重なった4月に1.9円上昇し税金5.1円を含め107円になりました。
8月の114円まで発表されていますが、税抜き108.6円ですので ボトム比+8.6円になっています。
建値分こそ何とかカバーしたものの、業転値上げ分の実質コストUPまでは、末端に反映出来て
いないのが実情ではないでしょうか。
その意味では、年末に94円程度であった激戦区市況は、8月現在税込み108円(税抜き102.8円)
で、8.8円程上昇していますが、激戦区のSSの多くは、業転市場からの購入の割合が高かった
のが一般的なので、今回のコストUPは、業転価格の上昇分をまともに受けることになります。
それでも、もし未だに108円というような末端SSがあり、それがもし元売の資本参加特約店の
直営SSなら、明らかな差別対価仕切が存在するのではないかと疑いたくなります。
ちなみに当社の9月価格ですが、現在の販売価格は全国市況並みなので、税込み118円を
お願いしたいと思っております。もし「高いなあ」とお感じになるお客様は、上記表の14年前の
湾岸戦争当時に末端価格 134円(税抜き)と比較戴ければ幸いです。この間、自由化や過当
競争でここまで業界マージンが減ってしまったことも合わせてご理解戴けば幸いです。
 お客様にちゃんとご説明し、更に対話をし、ご納得戴いた値上げをしていきます。
お客様にちゃんとご説明し、更に対話をし、ご納得戴いた値上げをしていきます。さて8月の日本は、オリンピックのメダルラッシュに沸いて、テレビや新聞等のニュースで、原油
価格の歴史的な高値話題は、殆ど取り上げられてこなかったのではないでしょうか。
しかし、我々販売業者は、「原油価格の記録的な上昇」という原因がこれだけハッキリしている
値上げですので、自信を持ってご説明し転嫁をお願いすべきでしょう。
そして、SSを経営している経営者や運営者としての我々は、掛売りのお客様だけでなく、例え
現金販売のお客様に対しても、「単に看板表示価格を9月から上げればよい」ということではなく
この「歴史的な原油価格の高騰という背景」をよくよくご説明し、お客様と対話し、そして
「ご納得して頂く」ことが大切なのではないでしょうか。
当社SSでは一般紙や業界紙を問わず、原油価格の高騰記事があると、それを各SSに配布し
各SSのレジカウンターや休憩室の机、そしてトイレ等にも張り出しております。
また9月からお願いする具体的な価格や値上げ幅が決定してからは、掛売用のご説明のご案内
文を拡大コピーして店頭に張り出すようにしております。また所長や従業員には、
「お客様に自信を持ってご説明するとともに、これを良い機会ととらえ、お客様と対話してほしい」
と指導しているところです。
この企画や表に記載したデータも、その説明資料の一部であることは言うまでもありません。
今月に関しては、4月企画同様、特に事前のご連絡は必要ありませんので、SS経営者の皆様は
自称業界アクセス数NO1の当社HPの各種データをどうぞご利用下さい。
そしてもし「従業員がお客様と対話出来なくて困っている」という経営者がいらっしゃいましたら
間に合うかどうかは分かりませんが、前月企画の「社員教育や従業員満足度」の内容を参考に
して頂ければ幸いです。
ご意見ご要望ご感想はこちらから 垣見 裕司 2004/9月1日更新 Ver 1