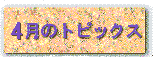
原油、業転、卸、末端の4価格、時期が重なった消費税総額表示を考える
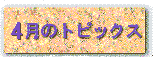 |
原油価格が反映しない末端市況は業界を滅ぼす? 原油、業転、卸、末端の4価格、時期が重なった消費税総額表示を考える |
 イラク戦争終結?にも関わらず、何故原油価格は高騰を続けるのか。
イラク戦争終結?にも関わらず、何故原油価格は高騰を続けるのか。産油国別原油価格ぺージ でも、 財務省発表の原油 通関統計 でも、現在の原油価格は
昨年2月のイラク開戦時の水準をついに突破してしまいました。少なくとも大規模な戦闘は終結
しているにも関わらず、何故ここまで原油価格は、高騰してしまったのでしょうか。
まず注目すべきは、2月のOPEC総会での減産決定です。その時点でも従来のプライスバンド
(22-28$/B)の上限状態にあるにもかかわらず、10カ国(イラク除く)計の生産枠を 2450万BD
から2350万DBへ 100万Bの減産を4月から実施すると決定しました。そして3/31にウィーンで
開かれた総会で、「増産か少なくとも減産は延期されるだろう」という消費国の希望を打ち消し
その減産を実施するということを確認しました。
従来は穏健派と言われたサウジですら「適正価格は25$/B」と言いながらも、その財政状態の
逼迫から本音は「30$/Bにしたいのではないか」という思惑もあり、高値維持の方針においては
OPECの意思と結束は固いようです。一方実際の生産量は2月で、2600万BD(MEES推定)と
相変わらず生産枠を大幅に上回っており、いつ価格下落し始めてもおかしくないという危機感が
予定通りの減産を決定させたとも言えるでしょう。
さて、原油価格の高騰原因として一般的に言われているのは、中国と米国の旺盛な需要と
米国の低在庫、そして戦争終結後も思うように生産を回復出来ないイラクの要因でしょう。
しかし、私は、従来から申し上げているように、これら実需の要因以上に、パレスチナ・ハマス
の指導者ヤシン氏が、シオニストに暗殺されたことによる中東全体の緊張状態を煽って市場を
過剰反応させ、その変動によって利益を得ようとしている「投機筋」が主犯ではないかと思います。
その動きは、例えば、イラク戦開戦と同時に価格が下がってみたり、米大統領のイラク戦終結
宣言で、逆に上昇してみたり、実需給とは逆張りの投資方針に現れていると思います。
そしてここからは全くの私見ですが、消費国の代表として、「原油高騰は世界経済の活力を
奪ってしまう」、適正価格での安定供給を産油国に働きかけている米国ですが、大統領の
出身母体を考えると、それがどの程度本気なのかは、多少疑問が残るところです。
 元売各社の需給調整で高騰を続ける業転市況
元売各社の需給調整で高騰を続ける業転市況これら原油の高騰は、石油業界の収益を間違いなく直撃しています。これを打開すべく
元売はまず原油処理減産と業社間転売市場の余剰製品の買い上げを徹底して行いました。
その結果、系列の卸価格より先に、業者間転売価格市場が高騰し始めました。
それでも過去の例なら、この対策をしている時期は、本来の市場価格より高く売れるので、
稼働率を上げ、コストを削減し、自分だけ利益を上げる(精製)元売がいて、必ずと言って
良い程、高市況は長続きはしませんでした。
しかし今回は、出光の苫小牧製油所の問題、そして各社がそれまでに地道に行って来た
精製設備の削減効果等が出て来たのでしょうか、民族系最大手元売が積極的に実践し
他の民族系はもちろん、さすがの外資系も独自判断で減産体制を取っているようです。
下記表は、ガソリンと灯油の業転価格の推移です。
原発特需も一段落し、全体の需要は決して多いとは言えませんが、年末に80円の水準まで
下がったガソリンが、2月以降上昇し、3月下旬には、87円台へと、大幅に上昇しました。
これはあくまでも、ひとつの目安ですが、精製元売と販売元売の利益を見るための売買価格
を仮に業転価格とすれば、精製元売が非常に利益を上げられる環境であることが分かります。
一方販売元売としては、非常に苦しい訳ですが、精製専業元売は一部ですし、販売元売は
精製元売の親会社に当たることが多いので、元売全体の利益を考える時は、両方加算した
利益幅で考えるべきでしょう。
 どうなる、エネ庁発表の系列卸価格 下記価格は、まだ消費税抜きの価格です。
どうなる、エネ庁発表の系列卸価格 下記価格は、まだ消費税抜きの価格です。
さてもう一つ参考となる価格は、エネ庁が石油情報センターを通じてSSから毎月直接ハガキで
収集している卸価格でしょう。必ずしも正確とは言えないと思いますが、弊社も実仕入価格を
記載していますので、当たらずしも遠からずであり、またその変化幅等は、多いに参考になる
と思います。2月までは既に発表済みで、3月と4月は、元売発表の値上げ幅と業転価格の上昇を
織り込んだ当社推定の見込み数値です。
 それでも反応が遅い国内市況は、業界を滅ぼす危機的状態。
それでも反応が遅い国内市況は、業界を滅ぼす危機的状態。それはでは、肝心の末端市況は、どうなっているのでしょうか。
今回の原油価格の上昇に伴い、過去前例がないかもしれませんが、それまで自ら市況を
下げていると批判の多かった、元売の子会社特約店が1月末頃より、「販売数量を落として
でも、市況を回復させよう」する決死の値上げ方針を打ち出し、実施したもようです。
そして市場に値上げ機運が高まり、他の民族系やそして外資系元売系列の特約店、そして
業転価格の上昇を見た商社系や大手広域デーラーも独自判断で値上げに踏み切りました。
その結果、激戦区では乱売合戦が一時収束し、2円程度の改善が見られたと思いますが、
石油情報センター発表の全国市況価格を押し上げるまでには、至らなかったようです。
ちなみにアメリカでは、1ガロン当たり2$という過去最も高い価格水準になっています。これは
原油価格の上昇だけでなく、低在庫や一部の製油所のトラブルが重なった複合要因でしょうが、
民主党が政府のエネルギー政策の失敗を追及するという政治問題にまで発展しているようです。
過剰に反応することは決して良いとはいいませんが、石油業界の自由化の基本理念であった
「国際価格に連動する国内市場価格」の建前からすれば、イラク戦争開始時の水準を突破し、
10年前の湾岸戦争以来の高値になっているにも関わらず、その国際情勢に全く反応しない
国内市況は、石油業界にとって危機的な状態と言えるでしょう。
 原油コストUP重なってしまった、消費税総額表示にどう対応すべきか。
原油コストUP重なってしまった、消費税総額表示にどう対応すべきか。この4月は、「販売価格表示を消費税も含んだ総額に変更する」という歴史的な時です。
石油業界も4月5日時点で、ほぼすべてのSSで看板価格等が、増額されています。
そして、ここまでなら、お客様も社員もそして国民も、「納得しているかどうか」は別として
少なくとも「ご承知」それていることではないでしょうか。
しかし肝心なのは、ここからです。末端SSが、2月以降元売から要請されている仕切値上げは、
既に3円程度、そして4月分だけでも 2-3円が通告されています。それは、前述の様に、原油が
上昇し、業者間転売価格も上昇している以上、やむを得ない仕切値上げでしょう。
この消費税の総額表示への改定時期に、単なる便乗値上げは絶対避けなくてはなりませんが
「原油価格の記録的な上昇」という原因がこれだけハッキリしている値上げですので、自信を
持って転嫁をお願いすべきでしょう。
 ちゃんと説明し、更に対話をして行きましょう。
ちゃんと説明し、更に対話をして行きましょう。従って、SSを経営している経営者や運営者の皆様には、掛売りのお客様だけでなく、たとえ
現金販売のお客様に対しても、誤解を招かないよう、この歴史的な原油価格の高騰を説明し
対話し、「ご納得して頂く」ことが大切なのではないでしょうか。
これは当社のSSでの話ですが、仮に3月末時点の看板価格が98円、4月1日が103円として
4月に来られたお客様に「高いじゃないか」と言われたときに、「消費税分しか上げていません」
と答えてしまいました。しかしお客様が前回来店されたのは、2月。その時は96円でしたから、
お客様の立場に立って考えれば、確かに値上げをしていました。そしてその時は、直ぐに
原油高騰や仕切UPをご説明出来る資料が、全てのSSに用意はされていませんでした。
そこで4月2日に急遽本社で作成し即日各SSに配布し、6日の所長会では、自信を持って説明
するとともに、これをむしろ良い機会ととらえ、お客様と対話をしようということになりました。
この企画のデータも、その説明資料の一部であることは言うまでもありません。今月に関しては
特に事前のご連絡は必要ありませんので、SS経営者の皆様は、自称業界アクセス数NO1の
当社HPの各種データをどうぞご利用下さい。
そしてもし「従業員がお客様と対話出来なくて困っている」という経営者がいらっしゃいましたら
間に合うかどうかは分かりませんが、前月企画の「社員教育や従業員満足度」の内容を参考に
して頂ければ幸いです。
ご意見ご要望ご感想はこちらから 垣見 裕司 2004/4月6日更新 Ver 2
 原油価格UPの番外編 予期せぬ副産物、それは石油株の高騰
原油価格UPの番外編 予期せぬ副産物、それは石油株の高騰4月1日、上場している石油元売会社の株が高騰しました。株式番号5001の新日本石油で説明
すれば、3/31の終値595円から、4/1は約5%も上昇625円に達しました。4/5では、日経平均の
上昇の流れを追い風に更に上昇し、640円(前場終値)となりました。
証券会社のコラム等には、「OPEC減産発表を受けて需給逼迫し高値が続く」とここまでは
当たりですが、「元売会社の収益増が見込まれる」はやや疑問です。というのも原油開発等の
上流の開発部門も勿論ありますが、新日本石油で言えば、それは総販売量のせいぜい10%。
後は在庫評価益が多少ある程度ですが、10年以上前のように末端価格への転嫁力があった
時期ならいざ知らず元売の価格影響力が、上記表の通り業転価格まであるように限定的であり
そして多くの販売子会社特約店を抱える今日の状況において、原油価格UPが即元売収益UP
とは言えないように思います。もっとも、本来の底力や、基幹産業として見直されての「買い」なら
私は大賛成です。