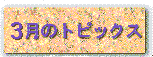
削減目標提出国数、ロウ戦争は終わるのか
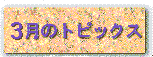 |
続エネルギー基本計画と環境問題を考える 削減目標提出国数、ロウ戦争は終わるのか |
 第7次エネルギー基本計画閣議決定 (3)石油関連
第7次エネルギー基本計画閣議決定 (3)石油関連
本基本計画は、原案の通り2月18日に閣議決定されました。
詳細はこちらの経済産業省のHPの通りですが、石油製品やSSそして
次項ではLPガスについて、要点をピックUPしてみたいと思います。
(3)石油(備蓄/サービスステーション(SS)等を含む)
① 総論
石油は、一次エネルギーの約4割を占め、幅広い燃料用途や化学製品等
素材用途を 持つ。調達に係る地政学リスクは大きく、また石油の国内需要
も減少傾向にあるが、 エネルギー密度が高く、備蓄体制が整備され、
可搬かつ貯蔵が容易であり、災害時に はエネルギー供給の最後の砦となる、
国民生活・経済活動に不可欠なエネルギー源である。
② 備蓄の確保 略
③ 石油供給体制の維持・移行 略
④ SSによる供給ネットワークの維持・強化
(ア)総論 SSは、給油や灯油の配送等を通じて国民生活や経済活動を
支える重要かつ不可欠 な社会インフラである。令和6年能登半島地震では、
自身も被災しながらも、道路寸 断により孤立状態にあった被災地内の
緊急車両や病院・避難所等への燃料供給に貢献する等、地域の燃料供給を
担うエッセンシャルワーカーとして活躍し、その重要性が 再認識された。
一方で、SSの多くは中小零細企業であり、乗用車の燃費向上等により
石油製品の需要が減少する中、人手不足・後継者難、施設の老朽化等の
課題も相まって、SS数も減少を続けており、平時のみならず災害時の
「最後の砦」として地域 を支えるSSネットワークの維持・強化に向けた
取組の強化が喫緊の課題となっている。
(イ)SSの経営力強化 平時からSSが健全に経営されてこそ、災害時に
「最後の砦」としての役割を果たし得る。SSネットワークの維持・強化の
ためには、賃上げ等による人材確保や設備 投資を図るべく本業である
石油製品販売で収益を確保することに加え、石油製品の販 売以外の収益
拡大や効率化等に取り組みSSの経営力を強化していくことが必要である。
一方SSの多くが資金的・人材的に困難な状況にあることも配慮しつつ、
事業の多角化やデジタル技術を活用した人手不足対策、事業承継・M&A・
グループ 化等、経営体質強化のための取組を、様々な支援施策を総動員
して後押しする。また、 SSが石油製品の供給を継続しつつEVへの電力
供給やFCVへの水素供給、合成燃 料やバイオ燃料の供給を担う「総合
エネルギー拠点」としての発展を目指せるよう後押しする。 55-56頁
 第7次エネルギー基本計画 (4)LPガス 初めて独立掲載された
第7次エネルギー基本計画 (4)LPガス 初めて独立掲載された
(4)LPガス
LPガスは、化石燃料の中で温室効果ガス排出が少なく、約4割の家庭に
供給され、備蓄体制も整備されており、可搬かつ貯蔵が容易で品質劣化
のない分散型エネルギーである。国内需要の8割を占める輸入先は米国、
カナダ、豪州で9割超と地政学リス クが低く、エネルギー安全保障にも
資するうえ、ボンベで全国のどこへでも供給可能 であり、災害時には、
病院等の電源や避難所等の生活環境向上にも資する「最後の砦」 としても
重要なエネルギー源である。
LPガスの備蓄については、有事の対応やアジアの需要増加に備え、現在
の国家備蓄・ 民間備蓄を合わせた備蓄水準を維持する。LPガス業界や
JOGMECと連携し、緊 急時を想定した国家備蓄基地からの放出訓練や
各地への輸送に係る詳細なシミュレ ーションを実施する。また、災害時に
備え、自家発電設備等を備えた中核充填所の新 設・設備強化を進める
とともに、病院・福祉施設や小中学校体育館等の避難所等にお ける備蓄
強化、発電機やGHP等の併設による生活環境向上を促進する。
「災害時石 油ガス供給連携計画」を不断に見直し、同計画に基づいた
訓練を実施するほか、スマ ートメーターの導入による配送合理化等の取組
を後押しし、人手不足な中でも安定供 給可能な体制を強化する。
なお、LPガスを巡る商慣行を是正し、消費者からの信頼を確保すべく、
過大な営業行為の制限等を内容とする新たな規律を設けたところ、その
実効性確保のため、関 係省庁とも連携し、違反行為の取り締まりや市場
監視・モニタリングを継続実施する。 58頁
 温室効果ガス削減目標 何と9割の締約国が未提出
温室効果ガス削減目標 何と9割の締約国が未提出
気候変動対策の国際的な枠組である「パリ協定」の締約国は、5年毎に
排出削減目標の提出が義務づけられていますが、その2月の提出期限に
9割の国と地域が間に合わなかったとの残念というかやはりと思うニュース
が入ってきたので紹介します。
2016年発効のパリ協定では、11月にブラジルで開催される第30回国連
気候変動枠組み締約国会議(COP30)の9ヶ月前までに、35年までの新たな
削減目標を示す必要があったのですが、私が調べた範囲では195の国と
地域のうち僅か16ヶ国しか提出されていないようです。ちなみに米国は
前バイデン大統領時に提出されたものなので脱退を表明しているトランプ
政権下では無効となるかもしれません。世界の3%しか廃出していない日本
は、世界に合わせた削減でよいと思うのは、私だけではないでしょう。
以下は全国地球温暖化防止センター発表の2021年の各国CO2排出量です
主な2035年目標提出国 2030年目標のみ提出国 米国 13.7% 2005年比61~66%削減 EU 7.7% 1990年比で55%減 英国 1.0% 1990年比で81%減 中国 32.0% GDP当たりでCO2を
2005年比で65%減日本 3.0% 2013年度比で35年60%減
40年度73%減インド 6.9% GDP当たりでCO2を
2005年比45%減カナダ 1.5% 2005年比で45~50%減
 ロシアは経済制裁の中、何故戦争継続が出来たのか
ロシアは経済制裁の中、何故戦争継続が出来たのか
ロシアが、2022年2月24日にウクライナに侵攻して丸3年が経ちました。
その時の報告は、22年3月ロシアのウクライナ侵攻と欧米の経済制裁、
臨時企画、サハリンⅡ LNG問題を考える
4月企画、ソビエト連邦とワルシャワ条約機構国の幻想の通りです。
私の当初の印象としては、西側諸国がほぼ一致して経済制裁をした
ので、当時のロシアのGDP世界11位 17107億USドルでは、2~3年
しか戦争継続は出来ないと思っていました。
しかしロシア国内がルーブル安になったりインフレになったのは最初
だけで、その後の国内経済は持ち直し、2024年のGDPは12位、
19044億USドルとむしろ増えているのです。
その理由としてはGDPの多くや国家予算の約3割を占める原油や
天然ガスという、仕入れがなく、利益幅の多い資源だったからでしょう。
確かに欧州等の西側諸国への輸出は間違いなく減ったのですが、
中国、インドやトルコなどへの輸出は4倍だそうで、24年のロシアの原油
輸出総額は1210億ドルと侵攻前の2021年より3%も伸びているのです。
一方ウクナイナの24年のGDPは1862億ドルで世界58位です。戦争前の
21年の56位1646億ドルより伸びているのは驚きですが、ロシアとは一桁
違うので戦争継続は、欧州と米国の支援に頼るしかないのが現実でしょう。
 トランプ大統領によるロシアウクライナ停戦協議の現実性
トランプ大統領によるロシアウクライナ停戦協議の現実性トランプ大統領は、就任前より公言していたロシアウクライナ戦争の終結
に乗りだしました。驚いたのはウクライナや欧州ではなく、先にロシアの
プーチン大統領と大枠を決めてしまったようです。そしてトランプ案がいや
なら今後は米国は戦争継続の支援はしないと言い切るのでしょう。
その案は、現在占領中の領土のロシア編入とウクライナ軍の撤退、未来
永劫NATOに加盟しないというウクライナとNATOの確約でしょう。
しかしウクライナとしては、到底飲めるものではありません。これを分かり
安く日本に例えるなら、北方領土問題を抱える日ロ関係において、2014年
クリミア半島ならぬ北海道を突如占領されてしまった。世界は怒っては
くれたけど具体的には何もしてくれなかった。そして2022年2月、突如
東北に攻め込んで来て、一時は首都東京も占領されそうな勢いだった。
今の膠着状態は、青森、秋田、岩手を占領されて、宮城の仙台が新たな
国境になりそうだという感じなのでしょうか。
しかし太平洋戦争を経験した亡き母が言ってました。毎晩、焼夷弾から
逃げなくてはいけない恐怖が終わるなら、日本が負けてもいいから早く
戦争が終わってほしい。最後はウクライナ国民が決めるのでしょう。