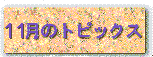
オイルサンドやGTLの競争力は、原油高騰を抑えられるか?
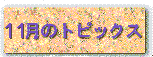 |
原油代替としての新燃料を考える オイルサンドやGTLの競争力は、原油高騰を抑えられるか? |
 新エネ法とは何か
新エネ法とは何か 1997年に「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(いわゆる新エネ法)」が施行されました。 対象は、太陽光発電、風力発電、太陽熱利用、温度差エネルギー、廃棄物発電 、廃棄物熱利用、廃棄物燃料製造、 バイオマス発電、バイオマス熱利用、バイオマス燃料製造、 雪氷熱利用、クリーンエネルギー自動車、 天然ガスコージェネレーション、燃料電池など様々です。
発足時は「脱石油」という発想があったために LPGは対象外でしたが、渡石油連盟会長の強い陣頭指揮のもと「脱石油」がなくなり、 LPGもよくやく導入支援政策の中に入りました。
しかし、上記にあげたものの中から近未来に原油や石油の「大規模代替」を可能にするのは、かなり難しいというのが実態のようです。
 古くて新しい オイルサンド・オイルシェール、オリノコタール(オリノコヘビーオイル)とは何か
古くて新しい オイルサンド・オイルシェール、オリノコタール(オリノコヘビーオイル)とは何かオイルサンドとは、流動性をもたない高粘度の重質油を含む砂ないし砂質岩のことです。
軽質分がなく残渣分であるアスファルトが主成分になっているものをタールサンドと言います。
いずれも通常の生産回収方式では坑井からは回収できず、露天掘りの状態で砂ごと採掘し
熱処理をしたり、高温の水蒸気等で砂と分離して原油を回収します。
オイルシェールは、炭化水素の根源物質である「ケロジェン」を大量に含む堆積岩の総称で
油頁岩とも油母頁岩ともいわれています。
オイルサンドの直近の埋蔵量は正確には報告されていませんが、サウジの原油埋蔵量である
2兆6270億バレルをしのぐ量だといわれ、その多くはカナダの中央部に埋蔵されています。
オリノコタールは、ベネズエラのオリノコ川北岸沿いに分布する長さ700km幅60kmのオリノコ
オイルベルトに埋蔵する超重質油です。既に商品化されているものは、オリマルジョンと呼ばれ
ある程度加工したオリノコヘビーオイルに水30%程度を混ぜ、更に微量の界面活性剤を加えて
主に発電用して使用されています。
このオリノコタールもその埋蔵量は1兆バレルを越えると言われています。
さて最も気になるところは、その生産コストです。オイルサンドは以前から1バレルあたり30ドル
と言われて来ました。従って私は業界に入りたての頃、原油は30ドル以上になると、莫大な
埋蔵量を誇るオイルサンドが採算に合い市場に出てくるので、原油はそれ以上上がらない
と教えられてきましたが、あれは嘘だったのでしょうか。
それは、投資家や上流部門を持つ企業経営者が30ドルを安定的にかつ長期に越えるような
原油価格を、誰も予想していなかったことが最大の原因でしょう。またプラント建設から商業
生産までかなり時間を要することも一因ですし、キャッシュフロー重視、また任期も1年という
短い期間で成績を出さなくてはいけないという昨今のビジネス界の風潮がそうさせているの
かもしれません。
 コスト以外にもあったオイルサンド等の問題点
コスト以外にもあったオイルサンド等の問題点しかし今となっては、新たなる大問題が出てきました。それは環境コストです。自然を大切
にするお国柄のカナダで、オイルサンドの大量生産を長期に始めたとなると、油まみれの、
そして産業廃棄物としての砂が内陸部で大量に出てくることになります。
一体それはどうやって処理したらよいのでしょうか。私が業界に入った頃とは環境に対する
考え方やその価値が高く評価されるようになった現在、その環境対策コストは、当時に比べて
はかりしれないくらい高くつくのかもしれません。
もうひとつは、加工して出来る原油の性状の問題です。オイルサンドにしても、オリノコタール
にしても加工して出来るのは、超重質油です。実は、前述の環境問題でも分かるとおり、
今世界のニーズは年々軽質油に移行しつつあります。WTIは軽質油ですが、中質油から
重質油が中心の中東原油との格差が、年々開くのもそこに問題があります。
また今の日本でも原子力発電所が順調に稼動してからは、C重油や昨今はA重油ですら、
相対的に余りがちになります。
従って埋蔵量が200年分といわれる石炭を粉状に粉砕し油とまぜた石炭系の燃料 COM
(Coal Oil Mixture)もその基礎技術は既に実用化され、試験も行われていますが、これも
重油代替としての利用に限られているので、軽質原油の代替としての利用は、むずかしい
のかもしれません。
 植物系燃料の長所と短所
植物系燃料の長所と短所では、サトウキビ、大豆、パームヤシ等の植物を発酵させて製造するバイオエタノール等の
植物系燃料はどうなのでしょうか。その強みは、なんと言っても京都議定書で認められた、
温室効果ガスの排出源として加算されないことです。それは植物系燃料が、炭酸ガスを
吸収して酸素を生成する光合成により作られた植物から出来ているためです。
しかし日本国内の資源は限られており、コストもかなり割高なので、やはり輸入に頼らざるを
得ないでしょう。現在輸出余力があるのは、事実上ブラジルのみ。しかしそのブラジルも
日本が大量に長期に購入をし始めれば価格は高騰するでしょう。また距離的にも非常に遠い
ので安定供給という意味では、問題が出てくるかもしれません。今の試算ではそのCIF価格は
原油より高いというシナリオもあるくらいです。アルコール燃料にも、その本来の目的である
道路利用並びに建設目的税である揮発油税が、もしかかるなら価格優位性は全くないと
いうのが私見です。
現在はガソリンに3%まぜるE3とか、10%混ぜたE10の実験が行われています。しかしガソリンに
アルコールを少しでも混ぜたその瞬間から、ガソリンは親水性となり水を含むようになります。
水は高温高圧では高度の腐食性を有する一方、ガソリンとアルコールを混ぜた燃料は、
有機溶剤と同様の性質を持つことからパッキン等のゴムや、場合によっては、エンジン内の
アルミ部品等を腐食させる可能性があります。
これは以前ある会社が高濃度のアルコールを含むガソリンを大量に販売していた時、
一部の車に不具合が出て大問題になりましたが、自動車メーカーが原因を分析したところ、
ガソリンに含まれていたアルコールが原因と分かり、各自動車メーカーは、「その高濃度の
アルコール混合燃料を使用しないように」との発表があり、今では法律で規制されるように
なりました。
 GTL(Gas to Liquids)やDMEは期待の星か
GTL(Gas to Liquids)やDMEは期待の星か私の考える最も期待の持てる「近未来の石油代替燃料」が一つだけあります。それは
天然ガスを合成して製造する GTL(Gas To Liquid) と呼ばれる液体燃料です。製造時に
硫黄などの不純物をほとんど除去出来ますし、 燃焼時の環境負荷も小さく、また天然ガス
の状態で輸送するより、液化すれば輸送や貯蔵が容易であるというおまけまでついています。
生成方法は、メタンガスを水蒸気とともに触媒存在下で高温(900℃)高圧化(30気圧)で
反応させるスチームリフォーミング法で、一酸化炭素と水素からなる合成ガスを生成させ
更に、中温中圧で触媒を用いるフィッシャートロプシュ(FT合成法)で生産されます。
南アフリカやマレーシアでは既に実用化済み、カタールでは、大型プラントを現在建設中で
2年後からは本格生産を始めるという話も聞いています。
この気になるGTLの製造コストは、25-30ドル/Bなので、現在の価格なら十分に採算に合い
ガソリン、灯油、軽油のいわゆる軽質白油の代替品としての使用が可能なので、正に
夢の燃料といってもいいでしょう。
また以前に本HPでも紹介したDME(次メチルエーテル)という製品も、ある意味このGTLの
一種です。DMEは、LPガスと特にブタンと性状が酷似しているので、貯蔵や輸送が容易で
あるだけでなく、既存インフラも使用出来るので、LPGや軽油の代替品として期待されています。
このGTLのプラントを立ち上げるプロジェクトは急速に進み、現在では昨年の3倍とも言われて
いるので、2-3年後からは、このGTLは原油市場に間違いなく影響を及ぼすでしょう。
天然ガスの確認済の埋蔵量も 70年以上と言われているので、数年後には、原油換算40ドル/B
以下のクリーンエネルギーGTLやDMEが供給されれば、必然的に原油価格も40ドル/B以下
に収まるのではないかと期待しています。
 気になる天然ガスの今後の中長期的価格とその埋蔵量
気になる天然ガスの今後の中長期的価格とその埋蔵量では気になる天然ガス埋蔵量や今後の価格予想はどうなのでしょうか。
ます埋蔵量ですが、2004年末現在で 世界で 6337,400bcf BP統計2005より(bcf=billion cubic
feet で 1bcf=0.028b立法メートル 約180兆m3)ありますが、石油業界の我々にはピンと
こないので、67年という可採年数の方が分かりやすいかもしれません。同時の原油の可採年数は40年なので1.5倍あるということだけでなく、原油の埋蔵量が60%も中東に集中しているのに対し、天然ガスは40%であり、世界に分散されていることがわかり、これも安定供給という意味では非常に大きな利点です。
また現在の原油生産量がMAXに近いのではないかという見方もある中で、天然ガスの方は
埋蔵は確認されているものの、買い手を捜してからでないと開発にかかれないというのが
現状だそうなので、開発資金と開発年数さえ考慮にいれれば、増産はいくらでも可能とのことです。
では価格はどうなのでしょうか。伊藤敏憲先生のご説明によれば、天然ガスの価格は以下図の
通り原油価格と多少の連動性は持たせているものの、開発時にその方程式をある程度FIXする
契約を締結するので、商業生産を開始してからの乱高下はないとのこです。
また、原油価格が今後も長期的に高止まりしても、埋蔵量や開発生産出来るプロジェクトは
多数あるので、現状維持か上昇しても緩やかな推移に留まるのではないかとのご説明でした。
従って原油が高騰しても、天然ガスは、短期的にも中長期的にも緩やかにしか上昇しない
というのが結論のようです。GTLという意味では喜ぶべきなのですが、都市ガスさんの仕入れが
これからも安定しているという意味では、非常に重要なことでしょう。ちなみに先生のご見解に
よればGTLと原油との損益分岐点は、原油価格で43ドル/Bとのことです。
天然ガス長期契約価格締結時の原油価格との連動イメージ(過去の一例)開発費は、ほぼ固定。その後原油価格が、例えば15ドル/Bまでは緩やかに上昇する。
15ドル/Bから25ドル/Bくらいまでは普通に上昇し、25ドル/Bを超えると再び緩やかとなる。
 天然ガスに唯一デメリットがあるとすれば
天然ガスに唯一デメリットがあるとすればさて、このバラ色のような天然ガスに唯一弱点があるとすれば、それは宿命のような「輸送」
の問題でしょう。天然ガスの利用は欧州で進んですいますが、ガス田とパイプラインで直接
それも網の目のように繋がっています。日本にもロシア等の産出地から直接パイプラインで
運べればベストですが、海をそれも遠浅の大陸棚ではなく、海溝を横断するのは、コスト的に
不可能といってよいでしょう。原油が枯渇し、その代替をすべて天然ガスに求めるような時が
万一来ればサハリンパイプラインのプロジェクトも採算に合うのかもしれませんが、現状では
イメージ先行のような気がします。
しかし1970年以降、天然ガスを圧縮して冷却して-162℃にまで更に冷却して液化し、LNG
として専用タンカーで運ぶという技術と物流が確立しました。液化すると体積が1/600になる
というメリットもあります。しかし0度近くで液化するLPGと比べ-162℃という温度は全く別世界
でしょう。都市ガスのHP検索した範囲内では、この液化プラントのコストや液化のための
ランニングコストは調べる事は出来ませんでしたが、それなりの環境負荷がかかっていることは
間違いありません。
またそれはLNGとして国内に輸入してからも同様です。パイプラインで繋がっているところの
大手工業用の都市ガス価格は、高騰した工業用灯油やA重油と同じか、場合によっては安く
なっていますが、パイプの来ていない地域にLNGタンクローリーで持っていくのでは、まだまだ
石油のコストには勝てません。
 伊藤敏憲先生ご提供のPDF(印刷不可)ファイル「新・代替エネルギーの現状」はこちらから
伊藤敏憲先生ご提供のPDF(印刷不可)ファイル「新・代替エネルギーの現状」はこちらから