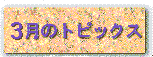
電気代、ガス代、灯油代の総合的な節約方&ローコスト化を考える
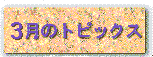 |
暖房エネルギーベストミックス探求記、NO2 電気代、ガス代、灯油代の総合的な節約方&ローコスト化を考える |
 反響の大きさに驚きました
反響の大きさに驚きましたCOP値5を超える最新の省エネエアコンのコストは、条件によっては灯油より安いかもしれない
この石油業界にとっての衝撃的な結論は、多くの反響を呼びました。これを読まれたある元売
の方が、技術担当者にその検証を指示し、私もその考察を頂きましたのでご披露致します。
1.実生活に基づいた視点と論理的に構築された考察に敬意を表します。
また当然ですが、当該条件の数値や計算等に間違いはないと考えます。
2.新築に際しロスナイを採用していることは、日頃の省エネと地球環境への配慮を感じます。
3.エアコン性能のCOP5や灯油とのランニングコストへの記述については、以下の通りです。
A 近年のエアコンの高効率は、コンプレッサーの回転UPと室外熱交換器の伝熱面積UP
によるところが大でありますが、この室外熱交換器の砂塵や汚れによるつまりによる
伝熱効果の低下によりCOP=4-5を維持出来る期間は長くないと見込まれます。
一般に室外熱交換器のクリーニングやメンテはあまり行われていません。
よって外気温分岐点は、もう少し高くなるのではないかと見込まれます。
B ヒートポンプエアコンは外気温により効率が左右します。
東京の一月の平均気温は5-6度で、日中を除くと、朝や夕方、深夜等の暖房必要時間
帯は、電気エアコンのCOP基準の7度下回る、外気温が低い時が中心です。
C チャンピオンデータを使っての結論は、消費者の判断を惑わす面もあるのかと考えます。
論より証拠で消費者が使って見れば、1ヶ月の電気代で明快になると思われます。
私も故障でもしない限り、室外機のメンテはした事がないので直ぐに納得してしまいました。
だた消費者の皆様には、私は暖かさの質の違いでアピールするのが一番よいと思います。
そして「論より証拠」で今回のマクロ実験の原動力になったことは申し上げるまでもありません。
一方石油関連団体等では「灯油はお得。都市ガスは3倍、電気は5倍」等の表現をしていますが
これはカロリー単価の話でエアコン等の機器によって異なることは、もうお気付きの通りです。
 今年の実験の目的は、電気、ガス、灯油の総合的な省エネと料金の低減化です
今年の実験の目的は、電気、ガス、灯油の総合的な省エネと料金の低減化ですさて今年の実験は「電気使用状況と分析とその低減」について掘り下げてみようと思いました。
というのも前回は電気使用量はあまり意識せず、都市ガスVS灯油の暖房機器のデータと
2ヶ月間の料金比較という、データを積み上げしただけで終わってしまった感がありました。
そこで今回は、電気、ガス、灯油全ての料金を把握しその合計データで比較することにしました。
具体的には、昨年1月に電気で823kWh、22,626円、都市ガス172m3、21,184円合計43,809円の
暖房コストを、灯油ファンヒーターを熱源として組み合わせベストミックスすることにより、
生活レベルを落とすことなく、すなわち体感温度を下げることなく、 如何に合計費用を削減する
かというものです。同時に、更に暖房コストではありませんが、照明等も含めてその他の電気
料金の削減も徹底的に実施して見ることしました。
 電気料金のデータの取得から
電気料金のデータの取得からまずは電気料金の調査です。請求書を紛失していても大丈夫。皆さんも是非挑戦して下さい。
まず東京電力のHPへ行き、「申し込み受付/生活・省エネ」 「電気のシェイプアップカルテ」
から「会員登録(お申し込み)(無料)」を申込んで下さい。すると1週間後くらいまでにアクセス用
のIDが届きます。それをHPに入力すると次のような画面をWEB上で見ることが出来ます。
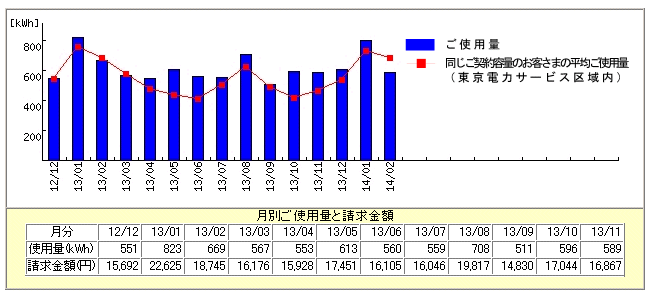
 意外に高かった我が家の通常月の電力料金 白熱灯を見直そう
意外に高かった我が家の通常月の電力料金 白熱灯を見直そうさてこの調査から、我が家の場合、非空調時の一般電力がそこそこ高いことが判明しました。
これは防犯上の理由他、屋外の常夜灯だけでも、勝手口1、外玄関1、内玄関2、外階段足元3、
駐車場2、庭2、建物2Fバルコニー4、など合計15箇所も付けていたからかもしれません。
もちろん外階段足元灯の6Wを始め、2階バルコニーは9W等、明るさは約4倍の電球色蛍光灯を
選定するなどランニングコストには意識しておりましたが、品揃えの関係で、40Wの白熱灯を
使用していたものが4つありました。そこで遅まきながらこれを、1箇所は20Wの蛍光等に、庭の
40Wの白熱灯は、9Wの電球型蛍光灯(電球色)に変更しました。
 白熱灯VS蛍光灯、投資コストの回収は出来るのか
白熱灯VS蛍光灯、投資コストの回収は出来るのかこの電球型蛍光灯は市価で1300円、 耐久性は6倍とのことですから、一般電球
を仮に130円とすると、130x4=520円分がランニングコストで回収出来ればよい
わけです。計算の結果(末尾参照)、残りのイニシャルコスト520円は、2.2ヶ月で
回収できることが分かりました。また過大であった駐車場40W蛍光常夜灯も20W
にしました。同様に室内も見直廊下等あまり重要でなさそうなところのダウン
ライトも60Wから40Wに変更するとともに、新築後、私の書斎?は、 60Wダウン
ライト4灯ですなわち240Wで生活しておりましたが、天井にコンセントはありますので 86Wの
電球色蛍光灯を購入して来た次第です。また子供がまだ小さく夜一人でトイレに行くため
にどうしても廊下に足元灯が必要になります。そこで究極の小型蛍光灯を見つけてきました。
100Vでコンセントに差し込むタイプですが消費電力は1W。西友で買ったのですが、メーカは(株)
オーム電気さんで価格も1000円しなかったと思います。もっともここまで行くともう「省エネお宅」
の世界ですから、もしHPを見て挑戦する人は楽しみながらやって下さい。
 電気料金の目標削減値は
電気料金の目標削減値はところで我が家の使用状況をみると最低がなんと9月で511kWhで14830円。冷房をつけている
季節なのに意外でした。もっとも次に低いのが、H12年12月の551kWhですが、これは翌1月が
823kWhと突出したので検針日が前後しているという期間日数の影響があるのかもしれません。
取り合えず、空調必要月以外の1ヶ月間の一般電力合計を 約560kWhとしてみましょう。
さて夏のピークは8月で708kWhで19817円ですがこれは我が家の食堂、居間、書斎、子供部屋
寝室の5部屋一ヶ月の冷房費用は148kWhx23円=3400円しかかからなかったいうことです。
日当たりの悪い家ではありませんからこれは省エネ高断熱住宅というハードの勝利でしょう。
一方冬場のピークは昨年1月の823kWhで、暖房電力263kWなら6049円ということになります。
しかし冬場は暖房以外に日照時間の短縮による照明電力増も考えなければなりません。
仮に照明合計500Wx4時間x30日=60kW とし夏の冷房電力にこれを加えた、760kWhあたりが
ひとつの参考目標値になりそうです。
 ご自分の契約アンペアをご存知ですか、過大な契約は必要ありません
ご自分の契約アンペアをご存知ですか、過大な契約は必要ありませんところで今回の実験で、やはりとんでもないことに気が付いてしまいました。
新築住宅は業界最先端の断熱性能住宅だったので、夏場の冷房においても、そこそこ節約
出来る自信があったので、設計時に電気契約容量を聞かれた際「60A」とお答えしました。
これは従量電灯Bの60Aの意味だったのですが、 住宅メーカーの設計の電気担当の方は、
部屋数や6台のエアコン数からして単層200Vの60Aすなわち、 従量電灯Cの12kVAと思った
ようです。両者の契約は、1kWh=23円の従量料金こそ同じですが、基本料金は、10Aあたり
260円違うので60Aでは、 なんと毎月1560円の基本料金の差になって現れることになります。
もしこの1,560円の差を例えば、60Wと40W 2灯の電球を消すことによって節約しようとすると、
月に何時間消せばよいか分かりますか。1560円/23円kWh/30日/ (60+40)W=22.6時間です。
毎日22時間も点灯している家は、ありませんから、220Wを毎日10時間消さなければならない
と考えてもよいかもしれません。これはやはりどう考えても無駄のようです。
早速、新築時にお世話になった電気屋さんに相談しましたところ、半分はお勧め出来ない
ということで、2/3の8KVA(80A)に下げることにしました。工事はわずか30分、費用は今回は
部品代だけてご了解頂きました。
 弊社社員のアンケートからは
弊社社員のアンケートからはさてこの基本契約問題は非常に興味のあるところだったので、協力してもらえる弊社社員に
お願いしたところ、興味ある例がいくつか出てまいりました。
A 契約30A 冬最大1月739kWh18,052円、夏最大7月445kWh10,702円、最小6月243kWh 5,727円
B 契約50A 冬最大1月344kWh 8,648円、夏最大8月466kWh11,779円、最小6月290kWh 7,354円
ちなみに社員Aは、たまにブレーカーが落ちることがあると言っていましたが、
では昨年1年間で何回落ちたかと聞くと、冬場に2回のみとのことでした。でも年に2回程度なら
ちょうどよい節電?警報装置と考えてみるのもよいような気がします。
ちなみに私のエアコンには省エネモードとは別にパワーセレクトモードというのがあって瞬間
最大電流を20Aから15Aに下げるモードがありますのでそれを有効活用するとよいでしょう。
一方社員Bは戸建ですが、比較的新しい住宅でした。一般に新築や築年数の新しい場合は
契約電流は、比較的多きめに契約されている傾向があるようです。
 ガス料金の実績把握
ガス料金の実績把握一方東京ガスにも自分の使用量を教えてくれるサービスがあります。
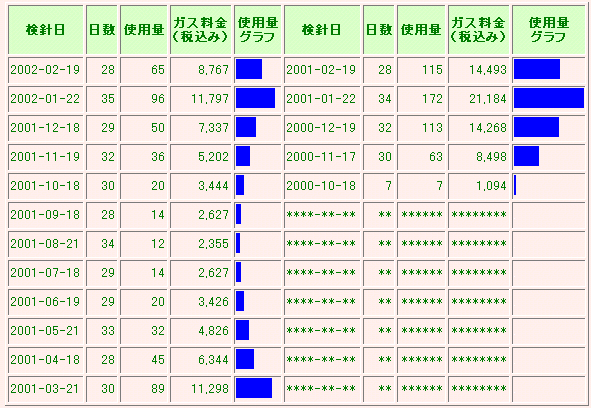
まず東京ガスのHPに行き「インターネットによる申込みとサービス」を選択「サービスメニュー」
「ガス使用実績紹介」のクリックで申込画面が出るのでそこに必要事項を書き込み送信すると
IDとPASSが送られて来ますので、それをHPに入力すると左表を見ることが出来ます。
また今シーズンから冬季に利用が多くなる床暖房向けユーザに「床暖房特約」があります。
これは家庭でガスを熱源とした温水床暖房使用ユーザーを対象にした新しい料金契約です。
条件を満たせば 床暖房だけでなく台所やお風呂の使用分もガス料金がおトクになります。
要するに基本料金が少し上がる変わりに従量料金が安くなり、使用量の大きいユーザーに
とって得になるシステムです。(右図参照) 早速申込んだことは、言うまでもありません。
 ガス料金の目標削減値は
ガス料金の目標削減値はさてガス使用量の増減をみて下さい。我々もLPガス販売業者として非常につらいのですが
ガスの使用量は、夏冬の差が、非常に大きいことがお分かり頂けると思います。
一般に灯油は気温によりその需要が変化するといわれていますが、ガスの場合は、気温に
加え水温に影響されるといわれています。特に夏の渇水時などはダムの水温が高くなり、
節水も手伝いお風呂やシャワー需要が低下するからです。しかし今回企画では販売業者の
立場をぐぐっと抑えて省エネローコストに徹してみたいと思います。
さてガス需要を考える場合は、寒くなるにつれ給湯に要するガスも増えてきますので、暖房
のみの需要増を推計することはむずかしいのですが、昨年1月の突出した使用量172m3を
灯油ファンヒーターの使用で、2月には115m3、3月には89m3に抑えられた実績があるので
床暖房の快適性や、快速暖房のガスファンヒーターの特性を生かしつつ、トータル的に
抑えてればよいという意味で、月間100m3程度をひとつの目安にしてみました。
 究極の省エネ節約法の実践
究極の省エネ節約法の実践そして昨年来より考えて来た究極の使用法の実践です。すなわち、外気温7度以下は灯油、
10度以上は電気エアコンの使用をベースにする一方、その暖房の質や暖かくなるまでの速度を
考慮し、朝起きた時は、家族の在宅時間が短いで、灯油とガスファンヒーターのみで過ごす。
幼稚園への送りや買い物後の帰宅後は、灯油Fヒーターで室温を上げ、その後は晴れていて
外気温が10度以上に上がっていたら、エアコンにて室温維持を図る。
午後の幼稚園のお迎えや買い物後以降の夕方は、外気温を見ながら順次灯油に切り替える。
しかし灯油ファンヒーターは、食堂、キッチン、居間全部を1台で暖める程の容量はありません
から、必要に応じ、ガスFヒーター、床暖房やエアコンを順次追加していくという感じです。
そして週末や休日、家族が居間で過ごす時間が長いときは、床暖房をメインにという感じです。
必然的に、直火を焚くファンヒータが多くなりますので、3時間で警告ブザーが鳴ったあとは、
ロスナイ等で換気を忘れては行けないことは言うまでもありません。
ちなみに、深夜私の書斎で長時間仕事をしなくてはならないときなどは、灯油Fヒーターを
移動して使ってみました。7畳の狭い部屋が、灯油ファンヒーターを焚くと、僅か10分で13度が
20度になりましたのが、外気温の低い時のエアコンにはマネの出来ない早業です。
 論より証拠、11月から2月までの4ヶ月間の結果は
論より証拠、11月から2月までの4ヶ月間の結果は
2001-2002年 今回データ 2000-2001年 前年データ 項目 11月 12月 01月 02月 合計 11月 12月 01月 02月 合計 改善 月間平均気温 13.1 8.4 7.4 7.9 約9.2 13.3 8.8 4.9 6.6 約8.4 +0.8 同平年比 +0.1 +0.0 +2.6 +1.8 +1.12 +0.3 +0.4 -0.9 +0.5 +0.1 +1.0 電力量kWh 589 607 802 589 2,587 625 551 823 669 2,668 -81 電力料金円 16,867 17,325 21,163 15,756 71,111 17,545 15,692 22,625 18,745 74,607 -3,496 ガス使用量m3 36 50 96 65 247 63 113 172 115 463 -216 ガス料金円 5,202 7,337 11,797 8,767 33,103 8,498 14,268 21,184 14,493 58,443 -25,340 灯油使用量L 38 60 83 80 261 0 0 25 58 83 +178 灯油料金円 1,406 2,220 3,071 2,960 9,657 0 0 1,000 2,320 3,320 +6,337 合計費用円 23,475 26,882 36,031 27,483 113,871 26,043 29,960 44,859 35,558 136,370 -22,499
まず東京の気温です。昨シーズンは寒いかと思いましたが平年比では1月が寒かっただけでした。
今シーズンは、11月12月が平年並みで1月2月はやはり暖かいようです。(データは気象庁HP)
ちなみに平均気温が1度違うと灯油全国需給が3から5%違うと聞いたことがありますので、もし
5%以上改善されていれば、コスト対策が有意性をもって、効果があったと言えるでしょう。
まず電気料金です。外気温10度以上の場合は、自信を持って電気エアコンを使用したので
電気量は81kWhしか減りませんでしたが、1月から契約容量の変更による基本料金の下げ
が効いて 3,500円のダウンとなりました。
都市ガス料金は最も減りました。昨年は4ヶ月で463m 58,400円も使用しましたが、
今年はなんと247m3、33,000円となり、25,340円の大幅ダウンです。
灯油は昨年40円/Lしていた価格が、今年は37円/Lと安くなったので安心して使用したところ
前年比 178L程多くなりましたが、費用的には6,300円増で済みました。以上総合して、
11月から2月までの4ヶ月間の電気、都市ガス、灯油のエネルギーコストは136,370円から
113,871円に22,499円、率にして16.5%も減少させることが出来ました。改めて申し上げれば
2001年1月に購入した灯油ファンヒーターは1台のみで、二階の寝室や子供部屋は、今年も
電気エアコンのみでしたから、これはの好結果だと思います。技術詳細資料は末尾参照。
 在室時間が長く広い部屋と、冬場の方が電気代が高いような使用形態は効果大
在室時間が長く広い部屋と、冬場の方が電気代が高いような使用形態は効果大さて今シーズンのカタログで最新エアコンのCOPを見てみましょう。調べた範囲ではN社が最も
良く、暖房で6.04冷暖計でも6.00の数値を6畳タイプの22型で出しています。しかしこれがより
大型の16畳タイプの50型となると4.32まで下がってしまいます。従って効率だけを見ると
電気エアコンは10畳用の28型程度までは、高性能のようです。灯油ファンヒーターは、6畳等
広くない部屋では換気の問題があるので、気密住宅では注意が必要です。
この両者の特徴を考慮し在室時間が長くLDKが繋がっていて様な広い部屋において
暖房器具として灯油ファンヒーターを併用するのが最も効果的のようです。
また前述の弊社社員Aのように、夏の冷房電力より冬の暖房電力の方が、大幅に高い
使用形態の場合にも、この併用暖房としての導入は非常に効果があると思います。
ちなみに私の購入したH社の灯油ファンヒーターは、今年も13,800円で販売していましたので
今回の実験からすれば1シーズンで元がとれたと言えるでしょう。
 室内燃焼機器からは、水分が出るのをご存知ですか?
室内燃焼機器からは、水分が出るのをご存知ですか?ところで皆様は、灯油やガスが燃焼すると水(水蒸気)が出来ることをご存知でしょうか。
詳しい理論や分子式は末尾に掲載しましたので我と思う方は挑戦してみて下さい。
この排出する水分量の質問をファンヒーターのメーカーに問い合わせたところ僅か10分で
「燃焼させた灯油とほぼ同量の水分が出ていると思って下さい」ご回答を頂きました。
実はこれは一般の加湿器と概ね同等の能力です。日頃の辛口?で喉にはあまり自信がない
私にとって、食堂と居間には加湿器が必要ないことはありがたい効果と言えます。
ただこれはあくまで結果であって、加湿器としてファンヒーターを利用して下さい。という
意味ではありませんので、くれぐれも誤解の無いようにお願いします。
では逆に結露の心配があるのでしょうか。以前住んでいた鉄筋コンクリートの集合住宅では
お風呂に窓がなかったことや、あまり広くなかったせいか、毎日のように結露していましたが
引越し以降は、LDKが連続していて広いことや、全室全窓が高断熱ペアガラスになって
いるので、結露で悩むということは、全くありません。
 高断熱、高気密住宅だからこそ、システム換気が必要なのです。
高断熱、高気密住宅だからこそ、システム換気が必要なのです。さて最近の新築住宅は、平成11年に改正された「改正省エネ法」や「住宅品質確保法」に
より設計されているので、高断熱高気密住宅になっています。その結果、室内燃焼型の暖房は
敬遠されている傾向がありますが、これは大変残念なことです。
例えば室内でタバコは吸えないのでしょうか。家族団らんでの鍋料理は出来ないのでしようか。
鍋奉行ではありませんが、やっぱり鍋は、炎で暖めて、食べるのが一番でしょう。
それこそ人間も1時間で400Lの廃ガス?を出しています。ではどうすればいいのでしょうか。
実は高気密だからこそ、効率的なシステム換気 が必要なのです。
通常は外気との温度差と排出口の高さを利用した自然換気で、二階の廊下の天井等から
温まった空気を屋根裏ダクトを通って屋根最上部の換気棟から出すシステムが一般的です。
自然換気の量は、温度差の激しい冬の方が多く、すき間指数が5cm2/m2の最新の住宅では
毎時0.5回から1回分の適正な換気が行われるよう「改正省エネ法」により設計されています。
それでも春や秋など、外気温との差がなく風のない日、換気量が0.1回/時にまで不足する
そうです。そこで私は、排気抱ダクト内に、電動ファンと風量調整ダンパーが内臓された、
ハイブリット換気システムにしました。僅か9Wの消費電力で、毎時1回くらいの換気が
確保されます。もちろん季節のいい時は窓をあけるのが一番良い訳ですが、騒音で窓が
明けられない場合等は、最初から考慮しておく必要がありそうです。
では新しい空気はどこから入るのでしょうか。私家ではペアガラスのサッシの枠に開閉可能な
換気スリットがあり、建物内が負圧になると少しずつ入ってくるようなシステムになっています。
更に在室時間の長い居間食堂等にはロスナイも入れましたので、これで換気はベストでしょう。
 私見ですが、結論をまとめて見ました。
私見ですが、結論をまとめて見ました。0.自分の電気代ガス代を一度しっかり調べて見る。問題があれば改善目標をたてる。
1.エアコンの購入は、COP値5以上の高性能のものがよい。特価品はCOP値を確認する。
2.6畳はエアコン。12畳等より広い部屋なら(併用)暖房として灯油ファンヒーターはより有効。
3.冬の電気代の方が、夏より高い人は、灯油ファンヒーターの使用が特に有効と思われる。
4.高性能エアコンなら外気温(約10度以上)によって、灯油よりコスト安になる可能性がある。
5.電気代の削減としては、常夜灯など点灯時間の長いものから白熱灯から蛍光灯に変える。
6.基本契約容量が住宅面積、生活人数、生活様式に対し明らかに過剰なら見直しも検討する。
7.灯油ガスファンヒーターは燃焼時水分が出るので暖房時の加湿器は必要ないかもしれない。
8.高断熱高気密住宅は、特に換気に配慮する。新築ならシステム換気、既設ならロスナイ等。
以上が2年間の我が家の実験の結論ですが、暖房に限らず何事もベストミックスの発想がよい
ように思います。また灯油ファンーヒーターが主暖房か補助暖房かは、読者のご判断ですし、
家の作りによっても違うと思います。また昨年企画からの上記4の結論は、2000年に新築した
高断熱高気密住宅で、業界最新式の高効率エアコンを用い、メンテナンスをして、その性能が
維持され、かつ外気温が7から10度以上である各条件を満たす、かなり狭義ケースであることを
誤解のないように、申し上げておきたいと思います。その他のいわゆる、暖房温度を1度下げる
冷蔵庫の設定温度を少し上げる等の一般的な省エネ対策は、 東京電力、 東京ガス
省エネルギーセンターのWEB等を参考にすると良いでしよう。
 技術資料 自信のある方だけでも是非読んで下さい。
技術資料 自信のある方だけでも是非読んで下さい。1.一般白熱灯から電球型蛍光灯への変更時のコスト回収
白熱灯130円、電球型蛍光灯1300円 但し耐久性は6倍とする。
1日12時間点灯するとして消費電力の差は 38-9=29W。
1ヶ月間では29Wx12hx30日=10,440Wh=10.4kWh 1kWh=23円で 240円の差となります。
耐久性以外のイニシャルコスト差520円/240円=2.2ヶ月 で回収できることとなります。
2.プロパン1KGを燃焼すると、どのくらいの水分が出るのか。
全ての気体は、0度C 1気圧で、22.4Lの体積を占めるめるというアボガドロの法則で
C3H8のプロパンガス1モルは44g、体積22.4L、その中に6.022x10の23乗の分子がある。
プロパンの燃焼式は、C3H8+5O2=3CO2+4H2O
44gのプロパンと160gの酸素の燃焼で、132gの炭酸ガスと72gの水蒸気が出来る。
仮に1m3すなわち1000L/22.4L=44.6モルのプロパンガスを燃焼したとすると
72gX44.6モルで 3211gの水蒸気が部屋の中に拡散されていることになる。
プロパンの真発熱量は21,800kcal/m3、、2180kcal=2.5kWのファンヒーターがあるとすば
運転時は、毎時 320gの水蒸気を放出していることになる。
3.灯油1Lを燃焼すると、どのくらいの水がでるのか。以下プロパンガスと同様に
灯油の分子式及び燃焼反応式は、 C12H26+18.55O2 → 12CO2+13H2O
灯油1モルの燃焼で水分が234g(13モル×分子量18)が発生する。
灯油1kgは、5.88モル、水分量は 234g×5.88モル = 1,376g。
灯油の比重は 0.79kg/L よって1,376gX0.79kg/L = 1,087g でメーカーの回答は正しい。
4.前年対比のエネルギー使用量分析
ガス削減量 216M3x9,930kcal/M3=2,145Mcal 灯油増加量 178Lx8,253kcal/L=1.469Mcal
に約30%の差があるのは、今年が少し暖かかったこと、灯油ファンヒーターの約100%の
熱効率に対して、ガス床暖房の熱効率60-70%との差、及び省エネ意識の3点によるもの
と思われる。 NO3 2/28 文責 垣見裕司