 早くも動き出した投機筋でWTIは急落、しかしその後再び上昇へ
早くも動き出した投機筋でWTIは急落、しかしその後再び上昇へ
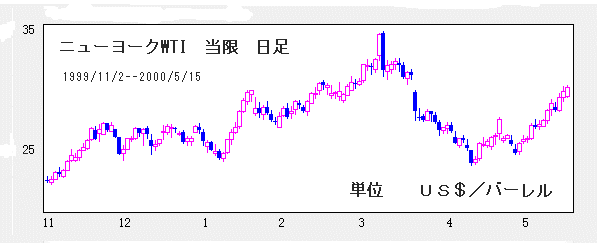
それではWTIはOPEC総会以降どのような動きを示しているのでしょうか。
実生産や実在庫ベースでは決して緩和とは言えないのですが、投機筋は「売り」と
判断したようで、総会前から図の通り値下げを始め3月8日の最高値34.37$/B
から4月10日の23.70$に31%も急落、しかしその後13日には一転25.96$
に2$以上も上昇し、かなり荒っぽい動きとなっています。
また14−17日のニューヨーク株式乱高下の影響を受け、嫌気した投機資金が
原油市場へ流れて来る可能性もあり、今後も荒っぽい展開が続きそうです。
そして5月に入ると上昇傾向は顕著となり15日には高値で30$を突破しました。
 プライスバンドとは何か、その効果はあるのか
プライスバンドとは何か、その効果はあるのか
しかしまだエネルギーの主役である原油価格が、短期間にこれほど乱高下することは
OPECにとっても消費国にとっても決して好ましいことではないでしょう。
実は今回の総会では正式発表こそされていませんが、ベネズエラ等が提案した
プライスバンドという方式が合意されたといわれています。これは、バスケット価格
(各国指標原油を色々織り交ぜて算出される価格)で22−28$/Bの間に価格を
納めようというもので、この価格が20日以上目標価格圏外で推移した場合は、
OPECは自動的に+−50万BDの範囲で生産調整するというものです。
しかしこの方式は18ヶ月前にベネズエラの鉱業相が提案を始めましたが、今まで
OPEC内の同意が得られなかった事、そして今回も非公式発表に留まっている事、
「価格」ではなく「在庫」で調整すべきだとの声もある事、そもそもOPECの
結束は未知数である事等、その効果を疑問視する声も少なありません。
 今後の原油価格はどうなるのでしょうか
今後の原油価格はどうなるのでしょうか
日本エネルギー経済研究所は12日OPEC総会終了後の原油価格展望を発表しました。
要約すると4月以降非OPEC諸国も加えると世界の石油供給は100万BDの純増
となるが、低水準に落ち込んでいる石油在庫を回復させるには不十分で、2000年の
需給はタイトな状況で推移する。価格レベルで言えば、WTIで24−26$、
ドバイで21−22$前後で推移する、と予想しました。
しかしその一方で当HPでも何度も申し上げている通り、現在の短期的な原油価格は、
石油産業に直接関係しない投機筋などの非当業者が、取引価格に大きな影響を与えて
いることを認めた上で、市場心理が再び強気に転じれば30$台もある。一方弱気から
先物下落となり弱気スパイラルが発生すれば20$割れもある、と言及しています。
更に申し上げれば、14日にニューヨーク証券市場の暴落をうけて17日の東京市場も
一時1800円近く暴落しました。この証券市場の動きを見て、石油先物市場からも
資金が逃げれば更なる下げも予想される一方、逆に資金が流入すれば更なる暴騰もあり
益々価格の振れが大きくなるのではないかと思います。
 コスト転嫁は約半分の国内市況
コスト転嫁は約半分の国内市況
では国内市況はどうでしょう。原油輸入価格の通り昨年1月輸入価格対比、本年3月の
予想ベースでは約10円/Lも値上がりしました。これを受けて日石三菱は、ガソリン
等代表的な石油製品で通算11.4円も値上げしています。しかし各油種の市況反映は、
石油情報センターの調査で、ガソリンSS店頭現金の全国平均99/4月の91円から
本年4月10日に100円に乗せ+9円となりましたが、軽油は昨年4月の76円から
本年4月の80円と+4円、また業務用のトラック業者様向けのインタンク価格も、
同様に5円程度しか上がっていません。灯油も情報センター調査で41円から44円
と僅か+3円ですから、フォーミラー価格で決定するC重油等産業用燃料を除くと
弊社の印象では卸価格上昇分の約半分というのが切実なる感想です。
 今後の業界に与える影響は
今後の業界に与える影響は
この値上げ未転嫁分の数字を年間総需要2億4千万KLの半分の1億2千万KLとして
5円/Lを石油業界で負担しているとすれば、この1年間で総額6000億円が業界から
消えたことになります。ですから来月からは、新聞等で日本への入着原油値下がりの
ニュースが掲載されることと存じますが石油業界としては約半分の取り残し分があり、
値下げどころか今までの値上げ未達分を消費者の皆様にお願いする状況であることを
ご理解頂きたく切にお願いする次第です。
そして連休等を期に再び乱売が始まれば、元売も流通もそれを吸収する余力はもはや
無く、その乱売は元売再編と流通業者の淘汰を益々加速することでしょう。
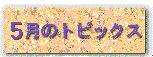
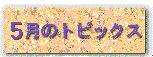
 総会で決定した内容
総会で決定した内容 145万B/Dという数字は本当に増産なのか
145万B/Dという数字は本当に増産なのか 早くも動き出した投機筋でWTIは急落、しかしその後再び上昇へ
早くも動き出した投機筋でWTIは急落、しかしその後再び上昇へ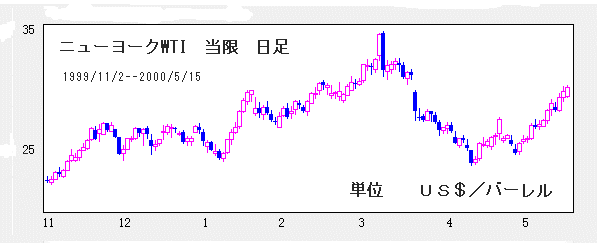
 プライスバンドとは何か、その効果はあるのか
プライスバンドとは何か、その効果はあるのか 今後の原油価格はどうなるのでしょうか
今後の原油価格はどうなるのでしょうか コスト転嫁は約半分の国内市況
コスト転嫁は約半分の国内市況 今後の業界に与える影響は
今後の業界に与える影響は