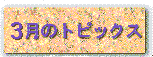
石油業界における不当廉売、差別対価、優越的地位の乱用を考える
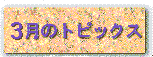 |
公取は石油業界を救えるか、高まる期待とその限界 石油業界における不当廉売、差別対価、優越的地位の乱用を考える |
 過去1年の動きをまとめてみると
過去1年の動きをまとめてみると 独占禁止法とは何か、石油業界でのポイントは
独占禁止法とは何か、石油業界でのポイントは以上2点は差別対価に当たるか、またそれは価格差にしてどの程度が許容範囲かに
ついて考えてみます。差別対価は上記一般指定では「不当に地域又は相手方により
差別的な価格をもって、商品若しくは役務を供給し…(以下略)」とされています。
ここで留意すべき点は、「不当に」(=公正な競争を阻害するおそれ)価格差を
設けることが禁止されており、必ずしも理由が付かない価格差があることだけでは
元売間競争の結果だと言われてしまうとそれが道義的には灰色でも現行法体系では
それだけでは違法とならないのが現実です
では何が公正な競争を阻害するおそれがあるかと見る点は、個別に判断するしか
ないのですが、典型的には元売業者が他の元売業者を駆逐するために特定の地域で
ダンピングをしかけるような行為が例として挙げられます。
また差別対価は同一の物でなければ成立しないことです。業転玉と系列品が同じ
品目と評価できるかという点がポイントですが、品質は同じでも元売得意の
ブランド料や品質保証を含む付加価値がついていると言われてしまうと、独禁法上
これを同一の物と評価するのは難しいように思えます。
ですから私もガソリン価格ページにありますように
原油に税金等を加えた小計Aが12.0円。経費小計B 8円のうち、97年度の
精製と販売変動費は、石油精製・元売全29社の平均で3.6円なので仮に4円とし
(精製変動費.副原料、薬品、燃料、電力・水道、外注作業費用等の合計1.65円)
(販売変動費.運賃、販売手数料、外注作業費用等の合計)1.95円で計3.60円)
それにガソリン税53.8円を加算すると届けで約70円という数字を下限指標。
また中部商品取引所の公の無印製品価格は届けで75円は、期せずして業転価格に
近く、これが継続的に供給されている現状を見てこれを中間指標。
そして一般特約店の系列仕切80円を上限指標として、具体例を出したかったので
すが、価格差だけの問題ではないことが分かり、誠につらいものがありました。
でもこの70円と80円。ガソリン税抜価格で比較すると16円と26円で高い
方から見ると実に38%値引きで、コスト論からでは説明の付かない訳です。しかし
販売業者から見れば許せない価格差でも、安い方の店は他元売との競争状態でその
元売にとって転籍されては困る重要な拠点なので安くした、という理由でOKなら
本当に恣意的な特約店選別もこの表現で通ってしまうので極めて危険だと思います。
それでも元売に対して何とかしたいというの方は、元売卸価格の「不当廉売」や
(某大手団体への販売価格や元売子会社の決算時や会社合併時の累積債務清算は
原価70円割れの価格で整理されていると推測出来る?るものがあるようです)
視野を広くして、親子会社間の利益移動のいわゆる移転価格問題や贈与税の発想
更に原価割れを継続しているのであれば株主代表訴訟の可能性もありますが、
これは独占禁止法の問題ではないことも付け加えなければいけません。
優越的地位の濫用の優越的な地位とは、当該事業者の要請が自己にとって著しく
不利益なものでも、経営存続上これを受け入れざるを得ないような場合を言います。
従って石油業界は、いやなら買わない更に転籍すればよい、という選択肢があり
今回エネ庁よりでた商標権に該当しない例の公表で、よりそれが広がった訳ですから
(系列元売から出た製品を同じ元売の商社や特約店から購入し販売したものやタンク
とノズルを分け、無印製品を販売していることが判別出来るなら、サインポールは
そのままでも商標権の侵害には当たらないという内容で歓迎しています。但し
サインポールはSS単位という個別契約がある場合はこの限りではありません。)
本件に関するガイドラインの策定は事実上難しいのではないでしょうか。
またこれは全く私見ですが、元売の社有SSの家賃については、共通指標を設ける
のがよいと思います。全部のSSは無理でも、ある特約店から返還されたものは、
販売数量などの下限をつけた上で系列内特約店で家賃入札するのが良いでしょう。
これにより価格が決まれば仮に元売の取得価格からの割り返しで赤字でも、もはや
元売は「贈与税がかかるので安く出来ない」とは言わなくなると思います。
 違反した場合の罰則は
違反した場合の罰則は 頼れるものは自分だけ
頼れるものは自分だけ 今こそモラルを
今こそモラルを