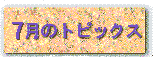
�����\�͂͏[������̂ɒn����`�ɓ͂��Ȃ����̗��R�@
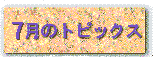 |
�q��R�����Ȃ����Ė{���H �����\�͂͏[������̂ɒn����`�ɓ͂��Ȃ����̗��R�@ |
 �q��R���s����
�q��R���s����
�傾�����@�ւ̃j���[�X�����ł��ȉ��̗l�ɑ������݂��܂����B
�K���Ζ��ƊE�������A�����������Ƃ����L���͂Ȃ��悤�Ɏv���܂��B
���� �@�� �^�C�g�� �t�q�k 6��22�� ���o�V�� �m�А��n�����ōq��R���s���̍����� �����N 6��19�� �ǔ��V���n�k �n����`�ő��֒f�O�A�C�O�̍q���� �����N 6��18�� �����V���f�W �R���s���ō��ې�����Ȃ��H�n����`�Ŗ�艻 �����N 6��19�� �m�g�j �R���m�ۂł����C�O2�Ѝ��ې��^�q����ߐV��� �����N 6��18�� �Y�o�j���[�X �K���q�}�Ŏ��v�N���A�A���̐��m�ۂ֑� �����N 6��19�� �k�C���V���f�W �����K���q�ɂ��e���@�A���l��s���̉����œ_ �����N 6��18�� �k�C���V���f�W ���ے���ց@�T14�������~�@�R���s���ŐV���` �����N 6��10�� �k�C���V���f�W �q��R���s�������Ŋg��@���ېV�K�A�q��֒f�O �����N 6��8�� �k�C���V���f�W ���q�@�R���e�n�ŕs�����ւł����K���q�U�v�Ɏx�� �����N 6��19�� �q��V���� �J���K�����W�F�b�g�R�����苟���́u�ǁv�� �����N
 ���e��v���
���e��v���
�e�n�ŃW�F�b�g�R���̋����s����肪�����A�q���Ђ̐V�K�A�q�A���ցA
�`���[�^�[�Ȃǂ̐헪�ɉe�����������Ă���B���ɖk�C���ł͐V���`�A
�эL��`�B�k�C���ȊO�ł͍L����`�ȂǂŁA�R�������s�����̐����
�A�C�O�q���Ђ̗Վ��ւ�ւȂǂɎx�Ⴊ�o�n�߂Ă���B
���{�͑���}���Ƃ��āA���y��ʏȂƎ����G�l���M�[����
�u�q��R�����s���ւ̑Ή��Ɍ����������^�X�N�t�H�[�X�v�̐ݒu������
��1��ڂ̉��6��18���ɊJ�����B
����ɂ͖��Ԃ���q���ЁA��`�W�ҁA�Ζ������̂ق��A�Ζ��A���A
�S����`��������A���{���q�C�^�g�����A����̊֘A�ƊE�c�́B
������͍��y��ʏȍq��ǁA�C���ǁA�ό����A�����G�l���M�[�����Q���B
��1��ډ�ł́A�@��`�ɔR������������ۂɎg�p���郍�[���[��
�A���D�̕s���B�A�e�J���K�����~���ꂽ���Ƃɂ��A����i������
�q���Ђ����ցE�V�K�A�q�A�`���[�^�[��ݒ肵�悤�Ƃ��Ă��A�R����
�m�ۂ��邱�Ƃ�����ɂȂ��Ă���Ƃ����\�}�����炩�ɂȂ��Ă����B
��̓I�ɂ́A�k�C���̐V���`�A�эL��`�A�L����`������A
�W�F�b�g�R���̈��苟���Ɋւ���v�]�����q��ǂɊ��Ă���B
 ���y��ʏȂ̍q��R�������s���ւ̑Ή��Ɍ����������^�X�N�t�H�[�X
���y��ʏȂ̍q��R�������s���ւ̑Ή��Ɍ����������^�X�N�t�H�[�X
���y��ʏȓ��̂g�o�ɏ�L�̊������c��g�o���ݒu����܂����B
����1��ځ@2��ڂ̓��e�����J����Ă��܂��B
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk5_000154.html
�@6��18���̑�P�c������e�͂�����
�@�@�����R�@�����ǁi���y��ʏȍq��ǁj��o����
�@�@�����S�@�����ǁi���y��ʏȊC���ǁj��o����
�@�@�����T�@�����ǁi�����G�l���M�[���j��o����
�@6��26���̑�Q�c������e�͂�����
�@�@�����P�@�c������
�@�@�����Q�@�W�Ҕ��\�����i����q��j
�@�@�����R�@�W�Ҕ��\�����iBOAR�j
�@�@�����S�@�W�Ҕ��\�����i�k�C���G�A�|�[�g�i���j�j
�@�@�����T�@�W�Ҕ��\�����i�Ζ��A���j
�@�@�����U�@�W�Ҕ��\�����i���{���q�C�^�g�����A����j
�@�@�����V�@�W�Ҕ��\�����i�i��Ёj�S����`�������Ƌ���j
 ���̋��c��̕��猩���ė�����������
���̋��c��̕��猩���ė�����������
��L�̕����ɑS�Ėڂ�ʂ��̂͑�ςł��傤����A���̓ƒf��
�ȉ��ɗv�_��Z�߂Ă݂܂����B���p������6-18-5-2�ŕ\���܂��B
1�@�ߔN�������̓��p�����i�B2009�N���C�Εx�R�A2012�N��A
�@�@2013�N�R�X����o�A2014�N�i�w�����A2015�N�쐼�����A2023�N
�@�@�d�m�d�n�r�a�̎R�A2024�N�����R���@6-16-4-2�@5-2
�@�@�A���A�������̔\�͓I�ɂ͖��͂Ȃ��i�M�ҕ]�j
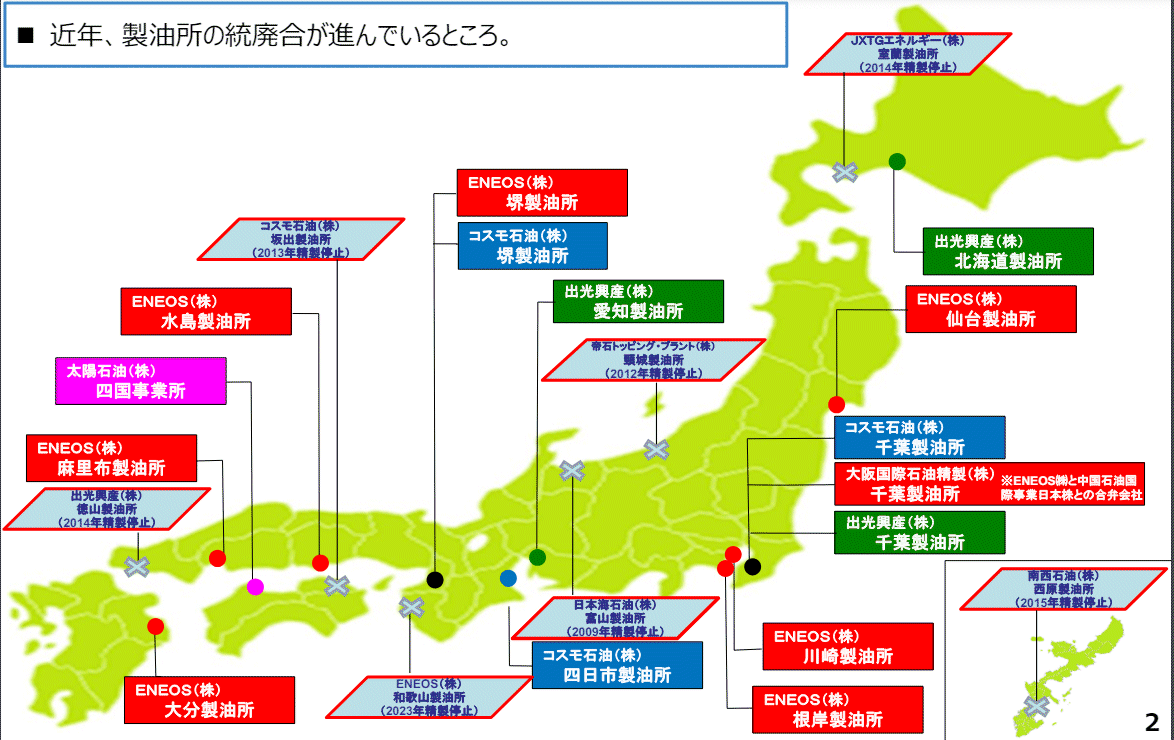
2�@���v���ɂƂ��Ȃ������^���J�[�̑��A���ʂ͉ߋ�30�N��
�@�@6���g������3.2���g���Ɍ������Ă���B6-16-4-1
�@�@����A���ʂƗA���������|�����킹���g���L����
�@�@2335���g���L������1618���g���L���Ɛ��ʂقnj����Ă��Ȃ�
�@�@����͐��������̌����ɔ��������������L�тĂ��邱�Ƃ�
�@�@�Ӗ����Ă���B
3�@�����^���J�[�┒���^���J�[�ǐ��͌������Ă���B
�@�@������^�����邱�ƂőΉ����Ă����B�@6-26-6-8-9�@�@6-26-5-3
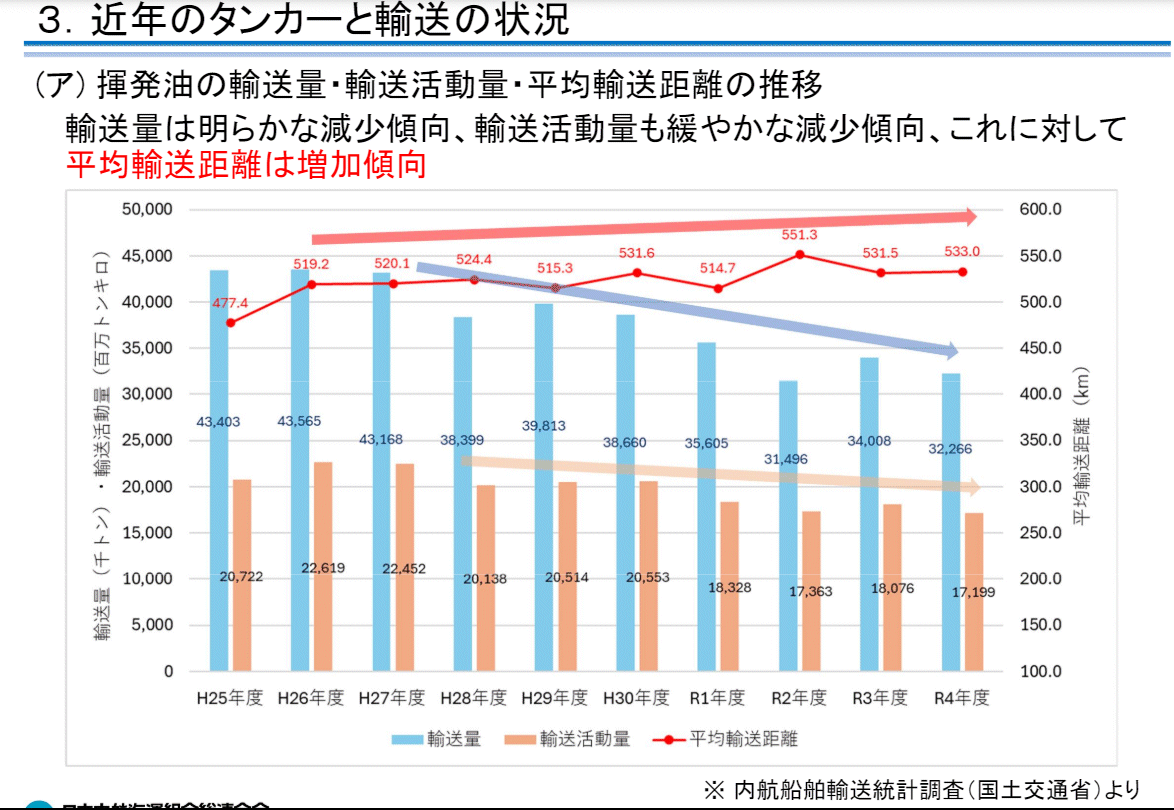
4�@�W�F�b�g�R���̎��v�͍��ې��̕���ꡂ��ɑ����B
�@�@�A���R���i�̎��Ɍ����������A���͂��Ȃ�����B�@6-26-5-1
�@�@�W�F�b�g�R���͊�{�͍������������A�K�v�ɉ����A�����Ă���B
5�@���������v�ŁA���q�D�̑D���������I�ɕs�����ғ������ቺ�����B
�@�@�܂��^���N���[���[�̃h���C�o�[����ɕs�����Ă���B��^�^�]�Ƌ�
�@�@�댯���戵���i�A�����Ƌ������K�v�ŁA�琬�Ɏ��Ԃ�������B
�@�@�@6-26-3-5-6
6�@���ɒn���̋�`�������Ǝ҂̋�����ƈ����s�����Ă���B
�@�@�q���Ђ��ƂɈقȂ鋋���v���g�R���́A�������̖W���ł���B
�@�@������ƈ��ɉߓx�ȕ��S�B��N�҂��̗p��������E���������B
�@�@6-26-5-7�@�@6-26-7
 ������s�@�ł��������ƍ��ې��ł͓��ڂ���q��R���̗ʂ��قȂ�
������s�@�ł��������ƍ��ې��ł͓��ڂ���q��R���̗ʂ��قȂ�
�F�l�A�{�[�C���O777-300ER�i���ې��d�l�j�̍ő哋�ڔR����
180�j�k�ŁA�h�����ʖ�900�{���ł��B��ɍ��ې��̂a787-10��126�j�k�B
�������Ɏg���\�肾����787-3��48.6���k�B�������͓���-�D�y�A
����-������������900�����B���ې��̓���-�j���[���[�N�Ȃ�11000�����B
�v����ɍs������l���ĔR�����ڗʂ����߂Ă���̂ł��B
��X���y�����܂߂Č���160�j�k��̔�����K�\�����X�^���h�́A�ʏ�
16�j�k�̃^���N���[���[�Ō�10��i3����1��j�B20�j�k��^�g���[���[��
�^���N���[���[�́A�~�n���L���̔��ʂ̑傫���r�r�����ɉ^��ł��܂��B
���������v�ł����ł����l��s���̃^���N���[���[�ƊE�B�V���`
�͓����̋�`�Ȃ̂ŁA�o���̓Ϗ��q����30KL�̃^���N���[���[�ʼn^���
����悤�ł��B�S���̃^���N�Ԃ̗Ⴆ�^�L1000�Ȃ�45�g������50�j�k��
�K�\������W�F�b�g�R�����^�ׂ܂����A���`�œS���̃^���N�Ԃ�
�������Ƃ͂���܂���B�Ϗ��q������`�܂Ŗ�20�j���B�p�C�v
���C��������Ό����I�Ǝv���܂��B�܂�1�N��ʂ��Ďg���Ă����̂ł�
�Ȃ��A�Վ��ււ̑Ή��ƂȂ�ƊW�҂̊F�l�̂���J�����@�����܂��B
 ���ʂ̑Ή���́A�Ζ��A���l�̒����p�����Ē����܂���
���ʂ̑Ή���́A�Ζ��A���l�̒����p�����Ē����܂���
�Ζ��ƊE�Ƃ��ẮA�������Y����{�Ƃ��A�K�v�ɉ����ėA�����s��
���ƂŃW�F�b�g�R���̗ʓI�m�ۂ��s���A�����������苟���ɓw�߂�B
����̎��v���������������苟���Ɍ����A�����A�g���Ĉȉ��̎�g��
�����ɐi�߁A�W���Ǝ҂̗\���������߂邱�Ƃ��K�v�B
�� ���q�ƊE�ɂ�������q�D�̑D���ʁE�D���̊m�ۂƁA����Ɍ�����
�@�@���̎x���Ƒ�
�� �l��s�����i�s���钆�A�O�q�G�A���C���̎��v�����ɑΉ������g���b�N
�@�@�ƊE�ɂ����郍�[���[�斱���̊m�ۂƁA����Ɍ��������̎x���Ƒ�
�� �������Ǝ҂̎��v������������������ƈ��̑����m�ۂƁA�����
�@�@���������̎x���Ƒ�
�� �q��e�Ђ��ƂɈقȂ鋋���v���g�R���̓��ꉻ
�� ���́A�V�K�A�q�E�����F�ɍۂ��A�����E�O���n���v���̊m�ۏ��
�@�@�����O�m�F
�� �Ζ���Ђ̐��Y�E���B�v��̌����Ɏ�����悤�O�q�G�A���C���̎��ԓI
�@�@�]�T���������m�x�̍����A�q�X�P�W���[���̒Ə��k�Ɍ���������
�� �֘A����K���̊ɘa �@���C���o�E���h�́A�o�ϐ����̂��߂̏d�v�Ȑ���
�@�@����ɌW��S�̓I�ȃt���[�����[ �N��Z�E�������I���_�Ŋ������A�g��
�@�@�v��I�Ɍ�������K�v������̂ł͂Ȃ����B
 �H�c��`�ɂ����鋋���v���Z�X�}�@���p���͂�����
�H�c��`�ɂ����鋋���v���Z�X�}�@���p���͂�����
���y��ʏȂg�o��蓌���H�c��`�̋����t���Z�X�}����肵�܂����B
�����^���J�[����`�ɐڊ݂�����A�p�C�v���C���Œ����^���N�ɒ���
�����o���闝�z�I�ȃV�X�e���ł��B�����Ȃ̂͂�������ŋ����ʂ̑���
���ې��̒��@�ꏊ�܂ŔR���p�C�v���~�݂���Ă���A�v������鋋����
�ɑ��ĘA���������o����n�C�����h�����V�X�e������������Ă��܂��B
�V���`�ł����̃n�C�����h�����V�X�e������������Ă���悤�ŁA
�����R�O�N ���ې��X�|�b�g���݂ɔ����n�C�h�����g�����z�Ǒ��݂��s��
�����E���ې��v�T�O�ӏ��� �T�U�ӏ��ɂȂ�A�ߘa�S�N�ɍ����E���ې�
���v�łT�U�ӏ����U�W�ӏ��ɑ��݂��ꂽ�ƕ���Ă��܂��B
 ���c��`�ɋ����v���Z�X�@���c��`�����{�݊������
���c��`�ɋ����v���Z�X�@���c��`�����{�݊������
�q��@�R���s�����́A�O�q�̒ʂ�ꕔ�̒n����`�̖��Ǝv����
���܂������A6��27���ɐ��c��`�̃g�b�v������J���A���c�ł�
�T57�ւ̐V�K�A�q���o���Ȃ��B�܂����c�ŋ����o���Ȃ��̂�
��q�������炵�ďo���n�ŋA��̔R���܂Őς�ŗ���ւ������
�R�����g���Ă��܂����B�@6��27���@���e���@
�������{�̊��`�ł��鐬�c��`�ł��R���s���ƂȂ�Ƙb�͕ʂł��B
�lj����������Ƃ��됬�c��`�����{�݁i���jHP�ɂ��ǂ���܂����B
�[�����@�́A��t�`���琬�c��`�܂Ńp�C�v���C�����ʂ��Ă��܂����B
�ȉ��@�q��R���A���V�X�e���@����̈��p�@
���c���ۋ�`�Ŏg�p�����q��R���́A�Ζ���А������Ȃǂ���
�^���J�[�ɂ��^��A �����p���̐�t�`���Ζ��^�[�~�i���ɉחg��
����܂��B��������S����47km�̃p�C�v���C���Ŏl�X���Ζ��^�[�~�i��
���o�R���āA���c���ۋ�`���̑�P�����Z���^�[ �܂ʼn^��Ē����B
��P�����Z���^�[����́A��`�̃G�v�����̒n���ɖԂ̖ڂ̂悤��
���݂��ꂽ�n�C�h�����g�z�ǂɂ��q��@�����܂ŕ��o����܂��B
�܂���Q�����Z���^�[�ւ��ڑ�����A��������܂��B ���p�I���B
 �e��`�̍q��R���̔[�����@�ƃ^���N�e�ʂƐ�����~�����@������
�e��`�̍q��R���̔[�����@�ƃ^���N�e�ʂƐ�����~�����@������
�ȉ��\�́A����Ԓm�肽�����e�ŏ����������ł��B�ŐV����������
�̕��͐����ĉ������B�����y�э��ۂ͕M�Ґ���̏o���ƒ�����
���킹�������B�����@�ɂ͋������Ȃ��̂ŁA�����Ώۂ͖�
�ȉ��Ƃ��܂����B�Α̑������͂����܂ł��M�Ґ���ł��B
��`�� �A�����@ �^���N�e�� ���� ����/�� ����/�� ����/�� ���c��` �p�C�v���C�� 144000KL 16.5�� 8683KL 140�� 600�� �H�c��` �����^���J�[ �@69400KL 6.6�� 10500KL 830�� 283�� �V���` �^���N��-��- 3000KL��4 6�� 2000�j�k 367�� 34�� �L����` �^���N��-��- �@800KL��3 6�� 400�j�k 54�� 4�� �эL��` �^���N��-��- �@200KL��2 6�� 60�j�k 14�� 0��
�@���c��`�͐��c���ۋ�`�i���j�g�o-2023�N�x���т�1������
�@�H�c��`�̔�����2023�N�x���ې����p���т�
�@�H�c�̍������͗��q�^�[�~�i�����p���т���̐���
�@�H�c��`�̋����ʂ͎O���I�u���l�g�o�@350��/���w30�j�k�Ő���
�@��ƑэL�͖k�C���G�A�|�[�g�l�g�o�@2024�N5�����є�����
�@�L���͍L�����ۋ�`�l�g�o�@2023�N�x������12�Ŋ���2�{
 7��23���lj��@�@7/16�̊������c��̓��e�͊�{���̊�{������
7��23���lj��@�@7/16�̊������c��̓��e�͊�{���̊�{������
7��16���ɊJ�Â��ꂽ3��ڂ̊������c��̓��e�����\����܂����B
�����N��قǓ��e�������Ȃ��̂ŁA�ȉ��Ɍf�ڂ��܂����B
�q��R�������s���ɑ���s���v��i�āj
�P�D�Z���̎�g
�@�@�@���v�ʂ̔c���@�e��`�ɂ�������v�ʂ̔c��
�@�@�@�����͂̊m�ہ@�W�F�b�g�R���̑��Y�A�A���̊g��
�@�@�@�A���̐��̋���
�@�@�@�@���[���[�y�ъ����D�̃t�����p�ɂ��A���͊m��
�@�@�@�@������ƈ��̊m�ہE�琬�Ɍ�������g�̋���
2. �������̎�g
�@�@�@�����͂̊m�� �E ���������y�ы�`�̃^���N�̑�����
�@�@�@�A���̐��̋���
�@�@�@�@���[���[�̑䐔�m�ہA�D���̑�^���A�V���������ז�ݔ��X�V��
�@���̓��e�����ā@���͋����܂����B
�@����ȓ�����O�̂��Ƃ��A�������߂Ċe�ƊE��e��Ђ�
�@�ʒB�i���肢�j���Ȃ��Ă͂����Ȃ����e�Ȃ̂ł��傤���B
����������肱�Ȃ��̂ŁA�Q�������W�҂ɂ��f�����Ă݂܂����B
�ȉ��͂��̏������ɂ����M�҂̐����ł�
1�@�e��`��Ђ͑��֓��̊�]�������i�K����@�e��`�̉^�c���
�@�@���тɊe�����Ə������𖧂ɂ���K�v������B
�@�@�@���̘A�����x���ƐΖ��������������̑��Y��s������ꍇ��
�@�@�@�W�F�b�g�R���̗A���v������Ă��Ȃ��B
�@�@�@�����̊m�ۂ����l
�@�@����ĐΖ�������Ђɑ��߂ɒm�点��d�g�݂�����
2�@�Ζ�������Ђ��O�N�䂾���łȂ��A���v�ɉ����������v�������
�@�@������_��Ɏ��s�o����悤�ɂ��Ȃ��Ă͂����Ȃ��B
�@�@�����ĐΖ��������q���Ђƒ���I���v���ȏ��������K�v